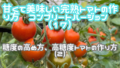イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方
はじめに
トマトは家庭菜園から商業栽培まで広く栽培される人気の作物ですが、その栽培にはさまざまな課題があります。その中でも病気の発生は、特に重要な問題の一つです。トマトは病気にかかりやすい作物であり、適切な対策を講じなければ、収量の低下や品質の悪化につながります。
トマトの病気は、カビ(糸状菌)、細菌、ウイルスなどが原因となるものが多く、それぞれ異なる発生条件や症状を持ちます。例えば、高温多湿の環境では灰色かび病や青枯病が発生しやすく、乾燥した環境ではうどんこ病が広がりやすくなります。また、アブラムシやコナジラミといった害虫がウイルスを媒介し、モザイク病などを引き起こすこともあります。これらの病気が進行すると、葉が黄変・枯死したり、果実に斑点ができたりして、最終的には市場価値の低下や収穫量の減少を招きます。最悪の場合、株全体が枯死し、大きな経済的損失につながることもあります。
しかし、病気の発生を完全に防ぐことは難しいものの、適切な管理を行うことで被害を最小限に抑えることは可能です。病害対策の基本は、**予防・早期発見・適切な対処** です。日々の観察を徹底し、環境管理や品種選定、土壌管理を適切に行うことで、多くの病気を未然に防ぐことができます。また、病気にかかってしまった場合でも、迅速な対応を取ることで被害の拡大を防ぐことができます。
本記事では、トマトに発生しやすい主要な病気の種類とそれぞれの特徴を解説し、具体的な予防策や対処法について詳しく紹介していきます。トマト栽培を成功させるために、病害の知識を深め、適切な管理方法を身につけましょう。
トマトの主な病気と症状
トマト栽培において、病気の発生は避けられない問題の一つです。特に、カビ(糸状菌)、細菌、ウイルスといった病原体による病気は、環境条件や管理方法によって発生しやすくなります。ここでは、それぞれの病気の特徴や症状、発生しやすい条件について詳しく解説します。
カビ(糸状菌)による病気
カビ(糸状菌)による病気は、高温多湿や風通しの悪い環境で発生しやすく、適切な湿度管理や換気が重要です。
うどんこ病

トマトの葉や茎に 白い粉状のカビ が発生する病気です。進行すると光合成が阻害され、生育不良や収量低下につながります。
症状
初期症状
・葉の表面に 白い粉をまぶしたような斑点 が出る。
・葉裏や茎にも広がることがある。
進行すると…
・白いカビが葉全体に広がる。
・葉が黄変し、枯れる。
・果実の着果が悪くなり、収量が減る。
原因
病原菌:(糸状菌=うどんこ病菌)
発生しやすい環境
・気温 20~25℃、湿度 低め(50~70%) で発生しやすい。
・ハウス栽培 で特に多発しやすい。
・風通しが悪い、窒素肥料の過剰施用で発生リスク増。
予防策
環境管理
・ 風通しを良くする(株間を広げる、不要な葉を摘む)
・窒素肥料を適量に(過剰施用すると病気に弱くなる)
・ 高温乾燥時期に注意(特に春~初夏、秋口)
物理的対策
・発病葉の除去(早期発見・除去が重要)
・耐病性品種の導入(うどんこ病耐性品種を選ぶ)
自然農薬(代替資材)
・重曹スプレー(水1L+重曹3g+食用油3ml)
・木酢液(1000倍希釈で葉面散布)
・酢スプレー(水1L+食酢10ml)
・カリグリーン(炭酸水素カリウム、食品添加物としても使用可)
治療(農薬)
発生初期に使用(病気が広がる前が重要)
農薬名 特徴
・モレスタン水和剤 予防・治療に有効、耐性菌リスクあり
・カリグリーン 炭酸水素カリウムが主成分、食品由来で安心
・トリフミン水和剤 予防効果が高いが、耐性菌リスクあり
・バイエルニンフロアブル 浸透移行性があり、持続効果が高い
農薬ローテーションが大切!
・同じ薬剤を連続使用すると 耐性菌 が発生しやすくなる。
・異なる成分の農薬を 交互に使う(ローテーション散布)。
まとめ
・風通しをよくし、窒素肥料を控えめにする。
・早期発見・除去が重要。
・重曹や木酢液など 自然農薬 で予防。
・発生したら 適切な農薬をローテーション散布 する。

うどんこ病が出やすい環境なら 予防策を徹底 するのが大切です!
灰色かび病

トマトの 葉・茎・果実に灰色のカビ が生える病気です。特に 傷口や枯れた葉 から感染しやすく、進行すると腐敗が広がります。
症状
初期症状
・葉や茎に 水浸状(しみのような)斑点 ができる。
・果実や花弁に褐色のシミが現れる。
進行すると…
・感染部分に 灰色のふわふわしたカビ が生える。
・葉や茎が 腐敗・壊死 する。
・果実が 腐る こともある。
特徴的な症状
・傷口や花がら(花の枯れた部分) から発症しやすい。
・雨が多い時期 や 湿度が高いハウス で発生しやすい。
原因
病原菌:(糸状菌=ボトリチス菌)
発生しやすい環境
・ 高湿度(80%以上) → ハウス栽培で特に多発
・ 気温15~25℃ → 春・秋に発生しやすい
・ 傷口や枯れ葉がある → そこから感染する
・ 密植で風通しが悪い → 湿気がこもりやすい
予防策
環境管理
・ 風通しをよくする(適度な剪定・葉かき)
・ 湿度を下げる(換気をしっかり行う)
・ 窒素肥料を控える(過剰施肥は病気を助長)
物理的対策
・ 傷をつけないように管理(誘引・剪定時に注意)
・ 枯れ葉・花がらをこまめに除去
・ 耐病性品種を選ぶ
自然農薬(代替資材)
・ 木酢液(1000倍希釈) → 殺菌効果あり
・ 重曹水(1L水+重曹3g) → 葉面散布で予防
・ 酢スプレー(1L水+食酢10ml) → カビ抑制
治療(農薬)
発生初期に使用(病気が広がる前に対処!)
農薬名 特徴
・ロブラール水和剤 灰色かび病に特化した殺菌剤
・フルピカフロアブル 予防・治療効果があり、耐性菌リスク低め
・スミレックス水和剤 予防・治療効果が高いが、耐性菌に注意
・ホライズン顆粒水和剤 浸透移行性があり、持続効果が高い
農薬ローテーションが重要!
・同じ農薬ばかり使うと 耐性菌 が発生しやすい。
・異なる系統の農薬を交互に使用 する。
まとめ
・傷口や枯れ葉を減らし、湿度管理を徹底する。
・ 風通しをよくし、過剰な肥料を控える。
・ 木酢液・重曹水 などの自然農薬で予防する。
・ 発生したら 早めに適切な農薬をローテーション散布 する。

灰色かび病は 湿度管理がカギ!
発生しやすい環境なら 早めの対策 をおすすめします。
葉かび病

トマトの葉に 黄色いシミ(斑点) ができ、裏側に かび(淡い紫~灰色) が生える病気です。放置すると葉が枯れて 光合成ができなくなり、収量が激減 します。
特に ハウス栽培 で発生しやすく、湿度が高いと 爆発的に広がる ことがあります。
症状
初期症状
・葉の表面に 黄色い斑点 ができる。
・葉の裏側に 淡紫色~灰色のカビ が発生。
進行すると…
・葉の色が 黄褐色→茶色 に変色し、枯れる。
・生育が悪くなり、果実がつかなくなる。
・果実には 直接病斑が出ない が、光合成不足で成長不良になる。
原因
病原菌(糸状菌=フルビア フルバ)
発生しやすい環境
・ 高湿度(90%以上) → ハウス栽培で特に注意
・ 気温15~25℃ → 梅雨・秋に発生しやすい
・ 密植・風通しが悪い → 湿気がこもると病気が広がる
・ 葉が濡れた状態が続く → 露・結露が原因になる
予防策
環境管理
・ 換気を徹底(ハウス内の湿度を下げる)
・ 密植を避ける(株間を広くとる)
・ 下葉かき・整枝を適切に行う(風通しをよくする)
・ 耐病性品種を選ぶ(葉かび病に強い品種を使用)
水管理
・ 葉に水をかけない(潅水は株元に)
・ 夕方の潅水を避ける(湿度上昇を防ぐ)
自然農薬(代替資材)
・ 木酢液(1000倍希釈) → 予防的に葉面散布
・ 重曹スプレー(水1L+重曹3g) → カビの発生を抑える
・ 酢スプレー(水1L+食酢10ml) → 菌の繁殖を抑制
治療(農薬)
発生初期に散布!(病気が広がる前に対処)
農薬名 特徴
・ダコニール1000 予防効果が高く、広範囲の病気に対応
・トップジンM水和剤 予防・治療の両方に有効
・STダコニール1000 耐雨性があり、持続効果が高い
・ザンプロDMフロアブル 葉かび病専用の治療薬
農薬ローテーションが重要!
・同じ農薬ばかり使うと耐性菌が発生 しやすい。
・異なる作用の薬剤を 交互に使用 する(ローテーション散布)。
まとめ
・ 風通しを良くし、湿度を管理する。
・ 葉を濡らさない・水管理を徹底 する。
・ 木酢液や重曹水 で予防。
・ 発生したら 適切な農薬をローテーション散布 する。

葉かび病は 湿度が高いと一気に広がる ので、発生前の対策が特に重要です!
すすかび病

すすかび病は、葉に黒いすすのようなカビが発生し、光合成が阻害されて生育が悪くなる病気 です。特に 湿度が高く、風通しの悪い環境 で発生しやすく、放置すると 葉が黄変し、最終的に枯死 することもあります。
原因は (クラドスポリウム菌) という糸状菌(カビ)で、胞子が風で拡散し、短期間で広がる のが特徴です。
症状
初期症状
・葉の表面に 黄緑色~黄色の不規則な斑点 ができる。
・葉の裏側に 黒いすす状のカビ(胞子) が発生する。
進行すると…
・葉の黄変が進み、光合成ができなくなり萎れる。
・葉が乾燥して パリパリに枯れる。
・重症化すると 葉が大量に落ちる(落葉)。
特徴的な症状
・カビ(黒い胞子)が 葉の裏側に集中的に発生。
・症状が進むと 葉脈に沿って広がる。
・風で胞子が飛散しやすく、周囲に感染が広がる。
原因
病原菌:(糸状菌=クラドスポリウム菌)
感染経路
・風や雨で胞子が拡散(特に密植すると広がりやすい)。
・葉水(葉が長時間濡れる)で感染が促進。
・前作の残渣(枯れ葉など)に菌が残り、翌年発生。
発生しやすい環境
・ 高湿度(75%以上) → 雨が多い時期に発生しやすい。
・ 気温20~25℃ → 梅雨・秋口に多発。
・ 風通しが悪い → 密植すると湿度がこもる。
・ 葉が長時間濡れる環境 → 夕方の潅水・梅雨時の長雨。
予防策
環境管理(最も重要!)
・適度な剪定で風通しを良くする(葉かき・脇芽かき)。
・ 雨よけハウスの設置(露地栽培では特に有効)。
・水はけを改善(高畝にする・マルチを活用)。
・ 耐病性品種を選ぶ(すすかび病耐性品種)。
水管理
・ 葉に水をかけない(株元潅水を徹底)。
・ 潅水は朝に行う(夕方の潅水は湿度を上げる)。
自然農薬(代替資材)
・ 木酢液(1000倍希釈) → 予防的に葉面散布。
・ 重曹スプレー(水1L+重曹3g) → カビの発生を抑える。
・ カリグリーン(炭酸水素カリウム) → 予防・治療効果あり。
治療(農薬)
発生初期に使用(早期発見が重要!)
農薬名 特徴
ジマンダイセン水和剤 予防効果が高く、広範囲のカビを抑える
サプロール乳剤 浸透移行性があり、持続効果が長い
ベンレート水和剤 予防・治療効果が高い
トリフミン水和剤 すすかび病専用で高い治療効果がある
農薬ローテーションが重要!
・同じ農薬を連続使用すると 耐性菌 が発生しやすい。
・異なる作用の農薬を 交互に使用(ローテーション散布) する。
まとめ
・剪定・風通しを良くして、湿気を防ぐ。
・葉に水をかけず、朝に潅水する。
・木酢液・重曹水で予防する。
・発生したら早めに適切な農薬を使用する(ローテーションが重要)。

すすかび病は 風で広がりやすく、発生すると被害が大きい ので、早めの対策がカギです!
疫病

疫病(えきびょう)は、葉・茎・果実が黒褐色に変色し、腐敗して枯死する病気 です。
特に 梅雨時期や秋雨の時期 に発生しやすく、湿気の多い環境で急速に拡大します。
病原菌は Phytophthora infestans(フィトフトラ菌) という卵菌類で、ジャガイモの疫病と同じ菌 です。雨が多いと爆発的に広がる ため、早期対策が重要です。
症状
初期症状
・葉に 水が染みたような不規則な斑点 ができる。
・葉の裏側に 白いカビ(菌糸) が発生することがある。
・茎にも 暗褐色の病斑 が現れ、徐々にしおれる。
進行すると…
・病斑が広がり、葉が黒褐色に変色し、枯れる。
・茎が 黒ずんで腐る(導管が詰まり、養分が届かなくなる)。
・果実に 茶色のへこむ病斑(湿った腐敗斑)ができ、腐敗する。
特徴的な症状
・病斑は 葉脈に沿って広がる ことが多い。
・湿度が高いと 病気の進行が非常に速い(1週間で全滅することも)。
・雨が続くと 爆発的に感染が拡大 する。
原因
病原菌:(フィトフトラ菌)(卵菌類)
感染経路
・雨や水の跳ね返りで菌が拡散。
・風による胞子の飛散(遠くまで感染が広がる)。
・ジャガイモからの感染(ジャガイモと同じ畑では特に注意!)。
発生しやすい環境
・高湿度(90%以上)(長時間の葉濡れがリスクを高める)
・気温15~25℃(梅雨・秋に多発)
・露地栽培・排水不良の畑(泥はねで感染が広がる)
・風通しが悪い(湿気がこもると発生しやすい)
予防策
環境管理
・雨よけを設置(露地栽培では必須!)
・風通しを良くする(適度な剪定・葉かき)
・排水を改善する(高畝にする・マルチを活用)
・耐病性品種を選ぶ(フィトフトラ耐性品種)
水管理
・水はけを良くする(過湿を防ぐ)
・潅水は朝に行う(夕方の潅水は湿度を上げる)
自然農薬(代替資材)
・木酢液(1000倍希釈) → 予防的に葉面散布
・重曹スプレー(水1L+重曹3g) → カビの発生を抑える
・カリグリーン(炭酸水素カリウム) → 予防・治療効果あり
治療(農薬)
発生初期に使用(早期発見が重要!)
農薬名 特徴
ランマンフロアブル 予防・治療効果が高い、耐雨性あり
ザンプロDMフロアブル 浸透移行性があり、持続効果が高い
リドミルゴールド 浸透移行性があり、耐性菌が出にくい
オキシンドーフロアブル 卵菌(フィトフトラ菌)に特化した治療薬
農薬ローテーションが重要!
・同じ農薬を連続使用すると 耐性菌 が発生しやすい。
・異なる作用の農薬を 交互に使用(ローテーション散布) する。
まとめ
・雨よけ・排水管理で湿度を抑える
・ 葉が濡れたままにならないようにする。
・木酢液・重曹水で予防する。
・発生したら早めに適切な農薬を使用する(ローテーションが重要)。

疫病は 雨が続くと爆発的に広がる ので、早めの対策がカギです!
その他の病気
立枯病(たちがれびょう)

特徴
・原因菌:リゾクトニア菌、フザリウム菌など
・影響:幼苗期に発生しやすく、発病すると茎が細くなり、倒れて枯れる
・症状:根元が褐変し、地際部から腐敗。萎れて生育が止まり、最終的に枯死
防除法
•土壌消毒:太陽熱消毒、薬剤処理(ベンチアバリス剤など)
•排水管理:水はけを良くし、過湿を避ける
•連作回避:同じ作物の連作を避ける
•種子消毒:種子に付着した菌を殺菌剤で処理
萎凋病(いちょうびょう)

特徴
•原因菌:フザリウム菌(Fusarium oxysporum)
•影響:主に成長期の植物に発生し、導管が詰まり、全体的にしおれる
•症状:初期は下葉から黄化し、次第に全体が萎れる
茎の維管束が褐変。水やりをしても回復しない
防除法
•耐病性品種の使用:フザリウム耐性品種を選択
•土壌消毒:クロルピクリンなどの土壌くん蒸剤を使用
•連作回避:特にナス科、ウリ科の作物は連作を避ける
•太陽熱消毒:夏季に透明ビニールを敷いて土壌消毒
根腐萎凋病(ねぐされいちょうびょう)

特徴
•原因菌:ピシウム菌(Pythium spp.)、リゾクトニア菌、フザリウム菌
•影響:根が腐敗し、水分や養分を吸収できず萎れる
•症状:根が黒く腐る。葉が黄化し、最終的に萎れて枯死
地際部の茎が細くなり、折れやすくなる
防除法
•土壌消毒:ベンレート、タチガレンなどの薬剤を使用
•排水対策:水はけの良い土壌環境を維持
•適切な施肥:窒素過多を避ける
半身萎凋病(はんしんいちょうびょう)

特徴
•原因菌:フザリウム菌(Fusarium oxysporum)
•影響:片側の葉がしおれる特徴があり、進行すると全体が枯れる
•症状:茎の片側だけが褐変し、葉が部分的に萎れる
根の発育不良、根腐れが見られる。 水を与えても回復しない
防除法
•耐病性品種の導入:半身萎凋病耐性品種を選ぶ
•土壌消毒:クロルピクリン、ダゾメットなどの土壌くん蒸剤を使用
•連作回避:フザリウム菌の蓄積を防ぐため輪作を実施
褐色根腐病(かっしょくねぐされびょう)

特徴
•原因菌:ロゼリニア菌
•影響:果樹などに多く発生し、根が腐敗して樹勢が衰える
•症状:根が褐変し、腐敗
葉が黄変し、枯死。進行すると木全体が衰弱
防除法
•感染株の除去:発病した株を早めに抜き取る
•土壌消毒:クロルピクリン、石灰窒素を使用
•水管理:過湿を避け、水はけを良くする
•堆肥の管理:未熟堆肥を避け、健全な土壌環境を維持
まとめ
病気の発生を防ぐためには、土壌の健全化、適切な水管理、耐病性品種の利用が重要です。
細菌による病気
細菌性の病気は、雨や灌水時の水のはね返り、傷口などを通じて感染します。特に高温多湿の環境では発生しやすくなります。
青枯病

青枯病は、トマトが突然しおれ、短期間で枯れてしまう細菌性の病気 です。
高温多湿の環境で発生しやすく、特に梅雨や夏場に多発 します。
病原菌は(ラルストニア・ソラナセアラム) という細菌で、
土壌や水を介して感染し、一度発生すると根絶が非常に難しい のが特徴です。
症状
初期症状
・日中に葉がしおれるが、夜間には回復する(初期段階)。
・葉の色は変わらず、青いまま萎れる(これが「青枯病」の由来)。
・葉脈に沿って黄化が始まることもある。
進行すると…
・全体的にしおれ、最終的に枯死。
・根から菌が侵入し、茎の導管が詰まるため水を吸えなくなる。
・茎を切ると、導管に褐色の変色が見られ、白い粘り気のある液が出る。
・被害株を放置すると、病原菌が土壌内で増殖し、他の株にも感染する。
特徴的な症状
・しおれても葉が黄色くならず、青いまま枯れる(葉焼けや乾燥ストレスとは異なる)。
・高温(25~35℃)で急速に進行 し、1週間以内に枯れることもある。
・土壌伝染が主な感染経路 で、根から侵入しやすい。
原因
病原菌(ラルストニア・ソラナセアラム)(細菌)
感染経路
・病原菌が土壌中に潜み、根の傷口から侵入。
・雨や灌水によって菌が広がる(感染拡大が早い)。
・連作圃場では土壌中に菌が残り、翌年も発生する。
発生しやすい環境
・高温多湿(25~35℃)で発生しやすい(特に梅雨~夏)。
・水はけの悪い土壌で発生しやすい(過湿で菌が繁殖)。
・トマト・ナス科作物の連作圃場で多発(菌が土壌に蓄積)。
・土壌がアルカリ性に傾くと発生しやすい(pH6.5以上は注意)。
予防策
土壌対策(発生を防ぐために重要!)
・連作を避ける(4~5年はナス科を作らない)。
・太陽熱消毒(夏場に透明マルチをかけて土を加熱消毒)。
・堆肥や有機物をしっかり分解し、土壌環境を改善。
・土壌pHを6.0以下に調整(酸性寄りにすることで菌の繁殖を抑える)。
水管理
・排水性を良くする(高畝にする・透水性の良い土壌を作る)。
・雨除けハウスの導入で過湿を防ぐ。
・株元灌水を徹底し、葉や土壌を不必要に濡らさない。
・耐病性品種の導入
・青枯病耐性品種を選ぶ(例:「耐病TY品種」)。
・接ぎ木苗を使用する(耐病性のある台木を使う)。
自然農薬(代替資材)
・バチルス菌資材(バイオスティミュラント) → 土壌病害の抑制。
・木酢液(1000倍希釈) → 抗菌作用で病害を抑える。
・納豆菌・乳酸菌資材 → 土壌の微生物バランスを整える。
治療(農薬)
発生初期に使用(早期発見が重要!)
農薬名 特徴
バリダシン液剤5 細菌性病害に効果、予防・治療に使用可能
ストレプトマイシン水和剤 抗生物質系、青枯病の進行を抑える
オリゼメート水和剤 土壌処理用、細菌の増殖を抑制
ユーラック水和剤 予防効果が高く、耐性菌対策にも有効
農薬の使い方のポイント
・発生初期に株元に散布し、菌の増殖を抑える。
・土壌処理と葉面散布を組み合わせると効果的。
・ローテーション散布を行い、耐性菌の発生を防ぐ。
まとめ
・連作を避け、土壌消毒を徹底する(太陽熱消毒・微生物資材の活用)。
・排水対策を行い、過湿を防ぐ(高畝栽培・適切な潅水)。
・耐病性品種や接ぎ木苗を利用する。
・青枯病が発生したら、速やかに抜き取って処分し、拡散を防ぐ。

青枯病は 一度発生すると根絶が困難 なので、事前の予防対策が最も重要です!
その他の病気
茎えそ細菌病

特徴
•原因菌:(リゾプシス菌)
•影響:ナス科(トマト、ナス、ジャガイモなど)に発生しやすい
•症状:茎や葉に黒褐色のえそ(壊死)斑点ができる
進行すると茎がひび割れ、内部が腐敗
葉に黒い斑点が現れ、やがて黄化・枯死
高温・多湿の環境で発生しやすい
防除法
•種子消毒:種子伝染するため、種子を熱湯消毒(50℃で25分)または薬剤処理(ストレプトマイシン剤など)
•水管理:過湿を避け、水はけを良くする
•土壌消毒:クロルピクリン、石灰窒素を使用
•耐病性品種の選定:耐病性品種を使用する
•感染株の除去:発病した株は早めに抜き取り処分
•輪作の実施:ナス科作物の連作を避ける(5年以上の輪作が望ましい)
斑点細菌病

特徴
•原因菌:(ザントモナス・カンペストリスパス・ベシカトリア)
•影響:ナス科(トマト、ピーマン)、アブラナ科(キャベツ、ブロッコリー)など広範囲の作物に発生
•症状:葉や果実に黒褐色の斑点ができる
斑点の周囲が黄色く変色し、葉が枯れる
進行すると果実や茎にも斑点が広がる
雨が多い時期や高湿度環境で拡大しやすい
防除法
•種子消毒:熱湯消毒(50℃で25分)または薬剤消毒(次亜塩素酸ナトリウムなど)
•耐病性品種の使用:斑点細菌病耐性品種を選ぶ
•水はけの改善:圃場の排水を良くし、葉が過度に濡れないようにする
•適切な施肥:窒素過多を避け、健全な成長を促す
•薬剤防除:銅剤(ボルドー液、酸化銅)やストレプトマイシン剤を散布
•感染株の除去:発病した葉や果実は早めに取り除く
まとめ
どちらの病気も 種子消毒、排水管理、耐病性品種の利用 が重要です。また、感染株の早期除去 も発生拡大を防ぐポイントになります。
ウイルスによる病気
ウイルス性の病気は、一度感染すると治療が難しく、主に害虫(アブラムシ、コナジラミ)によって媒介されます。ウイルスに感染した株は正常な成長が阻害され、収量や品質が大きく低下します。
黄化葉巻病

黄化葉巻病(TYLCV: Tomato Yellow Leaf Curl Virus)は、トマトの生育を大きく阻害し、収量を大幅に減少させるウイルス病 です。一度感染すると治療できない ため、予防が最も重要です。
この病気は、タバココナジラミ(Bemisia tabaci) という小さな害虫が媒介します。コナジラミがウイルスを持った植物から吸汁し、他の健康なトマトに感染させます。
症状
初期症状
・葉が縮れたり、波打つように変形 する。
・葉の色が薄くなり、黄化(黄色くなる) する。
・新芽が成長不良になり、葉が小さくなる。
進行すると…
・葉が巻き上がり(葉巻症状)、全体的に硬くなる。
・成長が大幅に遅れ、花や果実がつかなくなる。
・収穫量が極端に減少する(ひどい場合はほぼ収穫不能)。
特徴的な症状
・症状は新芽から発生し、上部に集中する(下葉は比較的健康)。
・発病するとウイルスが全身に広がり、治療不可能。
・トマト以外のナス科植物(ピーマン、ナス)にも感染する。
原因
病原体: トマト黄化葉巻ウイルス(TYLCV)(ウイルス病)
感染経路
・タバココナジラミが媒介(吸汁時にウイルスを伝播)
・感染した苗を植え付けると、畑全体に広がる
・ウイルスは種子では伝染しない(苗やコナジラミによる伝播が主)
発生しやすい環境
・気温25~30℃で発生が多い(夏~秋に特に多発)
・ハウス栽培で発生しやすい(コナジラミが繁殖しやすいため)
・近くにナス科の作物があると感染リスクが上がる
・防虫対策が不十分な場合、被害が拡大しやすい
予防策(最重要!)
タバココナジラミの防除(ウイルスの媒介者を防ぐ)
・防虫ネットを設置する(目合い0.4mm以下が理想)
・黄色粘着トラップを設置し、成虫を捕獲
・天敵(寄生バチ:エンストリウス)を利用する
・農薬を適切に散布し、コナジラミを駆除
ウイルスの侵入を防ぐ
・耐病性品種を導入する(例:「TY耐性品種」)
・感染苗を持ち込まない(購入時に確認)
・ナス科の雑草を除去し、感染源をなくす
環境管理
・換気を良くして湿気を抑える(コナジラミの繁殖を防ぐ)
・輪作を行い、ウイルスの蓄積を防ぐ
・被害株を早期に抜き取り、ウイルスの拡散を防止
自然農薬(代替資材)
・ニームオイル → コナジラミの忌避効果
・木酢液(1000倍希釈) → 病害抑制効果
・カリグリーン(炭酸水素カリウム) → コナジラミ対策
治療(農薬)
タバココナジラミの防除(ウイルスの媒介を阻止)
農薬名 特徴
・ベストガード水和剤 予防効果が高く、吸汁を防ぐ
・プレバソンフロアブル 殺虫効果が高く、耐性が出にくい
・アニキ乳剤 食毒と接触によるダブルの殺虫作用により、速攻的な効果を発揮します。
・アファーム乳剤 害虫の神経抑制伝達系に作用する「素早い効きめ」が特徴
散布のポイント
・ローテーション散布を行い、耐性がつかないようにする
・葉の裏側にしっかり散布する(コナジラミは葉裏に潜む)
・コナジラミの発生初期に散布し、増殖を抑える
まとめ
・タバココナジラミを防ぐことが最重要!(防虫ネット・農薬・天敵利用)
・耐病性品種を使う(TY耐性品種を選ぶ)
・感染した株はすぐに抜き取り、拡散を防ぐ
・ウイルスは治療できないので、発病しないよう予防を徹底する

黄化葉巻病は 一度発生すると治療ができないため、徹底的な予防が重要 です。
その他の病気
モザイク病

特徴
•原因:ウイルス(代表的なものは以下の通り)
•タバコモザイクウイルス(TMV):トマト、ナス、ピーマンなど
•キュウリモザイクウイルス(CMV):ウリ科、ナス科、マメ科など広範囲
•トマト黄化えそウイルス(TSWV):トマト、ピーマンなど
•影響:ウイルスによる感染で光合成が阻害され、生育不良を引き起こす
•症状:葉に濃淡のあるモザイク模様(黄緑や暗緑のまだら模様)が現れる
葉が縮れたり、奇形になる
生育が抑制され、果実の品質や収量が低下
一部のウイルスでは果実にも異常が現れる
防除法
•耐病性品種の使用:モザイク病耐性の品種を選ぶ
•媒介昆虫の防除:
•アブラムシ(CMVなどの媒介)を防ぐため、防虫ネットや薬剤散布(ピレスロイド剤、マラソンなど)を行う
•スリップス(TSWVの媒介)を防ぐため、黄色や青色の粘着トラップを設置
•ウイルスの物理的伝播を防ぐ:手や道具を介した感染を防止(特にTMVはタバコの葉や作業者の手を介して広がるため、作業前後に手や道具を消毒)
・感染株の除去(発病した株はすぐに抜き取り、焼却処分)
・土壌消毒:特にTMVは土壌中でも生存するため、クロルピクリンや蒸気消毒を実施
・連作回避:ウイルスが蓄積しやすいため、異なる科の作物と輪作する
まとめ
モザイク病は 予防が最も重要 であり、特に 媒介昆虫の管理 と 耐病性品種の選定 が効果的な対策になります。

トマトの病気には、カビ(糸状菌)、細菌、ウイルスが原因のものがあり、それぞれ発生条件や被害の広がり方が異なります。カビが原因の病気は湿度管理や換気で予防しやすいものの、細菌やウイルスは一度感染すると治療が難しく、予防が最も重要です。特にウイルス病は害虫の媒介によって広がるため、害虫対策が不可欠です。
次回では、これらの病気を防ぐための具体的な対策について詳しく解説します。