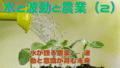イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方
なぜ「仕立て・摘葉・摘果」が重要なのか

トマトは、ただ植えて水をやるだけでは美味しく育ちません。元気な株をつくり、高品質な果実をたくさん実らせるには、「仕立て方」「摘葉」「摘果」といった丁寧な手入れが欠かせません。これらはすべて、トマトの力を最大限に引き出すための“育てる技術”であり、“愛情をかける作業”でもあります。
特に近年は、味の濃いトマトや高糖度トマトの人気が高まっており、収量だけでなく「質」が求められる時代になってきました。そんな中、トマト農家にとってはもちろん、家庭菜園を楽しむ方にとっても、これらの作業の意味とやり方をしっかり理解しておくことは大きな差につながります。
このブログでは、初心者の方にも分かりやすく、仕立て方、摘葉、摘果の基本とコツを丁寧に解説します。どんなタイミングで、どの葉を取り、どの実を残すのか――。日々のちょっとした手間が、味の決め手になることを、きっと実感していただけるはずです。
それでは、トマトと向き合う大切な3つの作業について、順を追って見ていきましょう。
仕立て方の基本 〜トマトの性格を読み解く〜

トマトは本来、旺盛につるを伸ばし、どんどん枝を広げていく性質を持っています。そのままにしておくと、葉や枝が込み合い、光が入らず、風も通らず、病気が発生しやすくなります。そこで大切なのが「仕立て」です。仕立てとは、トマトの樹形(姿)を人の手で整えること。適切な仕立てによって、健康な生育環境が保たれ、光合成が促進され、美味しい果実を効率よく実らせることができるのです。
仕立ての目的とは?
仕立ての目的は、大きく分けて3つあります。
光と風を通しやすくする
トマトの葉や茎が混み合っていると、下葉に光が届かず、病害虫の温床にもなります。仕立てによって枝葉の配置を整理することで、日当たりと通気性が格段に良くなります。
作業効率を高める
整然と仕立てられたトマトは、収穫や管理作業がとてもやりやすくなります。農作業の省力化にもつながるため、プロ農家にとっても欠かせない技術です。
株への負担をコントロールする
実を付けすぎると、トマトはすぐにバテてしまいます。仕立てによって適切に栄養を配分させ、長く安定した収穫を目指せます。
主な仕立て方の種類
トマトの仕立て方にはいくつかのパターンがあります。代表的なものを紹介しましょう。
一本仕立て(プロ農家向け/高糖度狙い)
主枝(最初に出てくる茎)だけを残し、他のわき芽はすべて摘み取る方法です。栄養が集中しやすく、果実の糖度が上がるため、高品質なトマトづくりに向いています。誘引とわき芽かきのタイミングが重要で、手間はかかりますが、味を追求するならこの方法がおすすめです。
二本仕立て(三本仕立ても含む)
主枝と、根元から出てきた最初のわき芽(第一花房の下)を残して2本立てにする方法です。一本仕立てより収量は増えますが、樹勢のバランスを取るのがやや難しくなります。露地栽培や家庭菜園では、スペースを有効活用できるためよく用いられます。
放任栽培
わき芽も剪定せず、自然のままに任せる育て方です。収穫量はそれなりにありますが、果実が小さくなったり、病気が出やすくなったりするデメリットもあります。手入れの手間を減らしたい初心者向けですが、品質重視の方にはあまり向きません。
わき芽かきと誘引の基本
わき芽とは、主枝と葉の間から出てくる新しい芽のことです。成長が早く、放っておくとすぐに太くなり、主枝と同じくらいの茎になります。このわき芽を適切に取り除くことが、仕立ての第一歩です。
• タイミング:わき芽が5cm以内のうちに摘み取るのが理想。大きくなってから取ると株にストレスがかかります。
• 方法:指でつまんで折るか、ハサミで切る(病気にかかっている場合はNG!)。雨の日は病気のリスクがあるので避けるのが無難です。
誘引とは、トマトの茎を支柱やひもに沿わせて、上に真っすぐ伸ばす作業のこと。茎が太る前に軽く結び、重くなった果実で倒れないよう支えていきます。強く縛りすぎると茎が傷つくため、ゆるめに8の字に結ぶのがコツです。

このように、トマトの仕立て方は「見た目を整える」こと以上に、光・風・栄養の流れを意識した、非常に合理的で繊細な技術です。次章では、仕立てと並ぶ重要な作業、「摘葉」について詳しく見ていきましょう。
摘葉の役割とタイミング 〜葉を取るか残すか、それが問題だ〜

トマトの葉は、光合成を行い、株全体にエネルギーを供給する重要な器官です。しかし、必要以上に葉が茂ると、逆に果実の発育や株の健康を妨げてしまうことがあります。そこで必要になるのが「摘葉(てきよう)」という作業です。摘葉はただの剪定ではなく、トマトの生命力と向き合う、繊細な判断を要する“呼吸の調律”ともいえる作業です。
摘葉の目的とは?
摘葉には、大きく3つの目的があります。
光と風を通すため
葉が茂りすぎると、内部に光が届かなくなり、湿気がこもって病気(特に灰色かび病、葉かび病、疫病など)が発生しやすくなります。摘葉によって通気性と日照性を確保することは、病気予防の第一歩です。
果実の糖度を高めるため
葉を適度に取り除くことで、果実に日光が当たりやすくなり、着色がよくなるだけでなく、光合成による養分が実に集まりやすくなります。とくに高糖度トマトを目指す場合、摘葉の仕方が味に大きく影響します。
作業性の向上
茂りすぎた葉は、収穫や病害虫のチェックを妨げます。スッキリと整理された株は、毎日の管理がしやすくなり、結果的にミスや病気の早期発見につながります。
摘葉のタイミングと優先順位
摘葉には「やるべき時期」と「やってはいけない時期」があります。焦らず、株の状態をよく観察して判断しましょう。
基本のタイミング
• 1段果の収穫が始まる頃
この時期に、1段果の下にある古くなった葉を中心に取り除きます。
• 果実の肥大期〜色付き始め
光がしっかり果実に当たるように、花房の下の葉を1〜2枚程度残して、それより下の葉を取ると効果的です。
• 病気が出た時・高湿度時
灰色かび病や疫病が発生しやすい時期(梅雨など)は、通気性を高めるために思い切った摘葉が必要なこともあります。
優先して取るべき葉
• 地面に近く、すでに役目を終えた葉
• 病斑や傷みが見られる葉
• 他の葉や実に触れて密になっている葉
ただし、株全体の葉の3分の1以上を一度に取ってしまうと、光合成能力が大きく下がり、株が弱るため要注意です。あくまで徐々に、バランスを見ながら進めていくのがコツです。
摘葉の実践テクニック
どのくらいの頻度でやる?
基本的には1週間に1回程度のペースで、全体の様子を見ながら数枚ずつ摘み取っていくのが理想です。毎日少しずつ観察する習慣があれば、自然と最適なタイミングが見えてきます。
摘葉は晴れた日の午前中に
葉を切った部分は「傷口」です。湿度が高いとそこから病原菌が入りやすくなります。天気の良い日の午前中に行い、日中のうちに傷口が乾くようにすることでリスクを最小限に抑えられます。
葉の残し方にもセオリーがある
• 花房の直下の葉はなるべく残す:その葉が果実への栄養供給を担っているため。
• 上部の若い葉はできるだけ温存:これからも光合成で株全体を支えてくれる重要な部分です。
失敗例に学ぶ摘葉の注意点
• 摘葉しすぎて葉が少なくなり、果実が日焼けした(サンバーン)
• 株全体の元気がなくなり、花が落ちたり、生育が止まった
• 花房のすぐ下の葉を取ってしまい、果実の肥大が不十分になった
摘葉は取り除く行為であると同時に、残すべき葉を見極める技術でもあります。その判断力こそが、トマト栽培における一流とアマの違いを分けるのです。

摘葉は、ただの剪定ではありません。株の体調を見極めながら、適切な葉を残し、必要な分だけ取り除く。その繊細な作業は、まさにトマトとの「対話」そのもの。
摘果の基礎と実践 〜果実に“選ばれし運命”を与える〜

「どの果実を残し、どの果実を摘み取るか」――摘果は、トマト栽培においてもっとも悩ましく、そしてもっとも奥深い作業です。丹精込めて咲いた花が実になり、その中から自らの手で“間引く”という決断は、まさに農家の心を試される瞬間といえるでしょう。しかし、摘果の目的と理屈を理解すれば、果実の質も収量も大きく向上させることができるのです。
なぜ摘果をするのか?
摘果とは、着果した実の一部を意図的に取り除く作業です。その目的は大きく3つにまとめられます。
果実一つひとつの品質を上げるため
実が多すぎると、1つあたりに行き渡る栄養が不足し、糖度が下がったり、サイズが小さくなったりします。摘果で数を絞ることで、残された実に栄養が集中し、味・色・形ともに優れたトマトに育ちます。
株への負担を軽減し、全体の生育を安定させるため
一時的に多く実らせると、株が疲弊し、その後の段の花付きや果実肥大が悪くなることがあります。摘果により、株のエネルギー配分をコントロールすることが可能になります。
収穫スケジュールを整えるため
肥大が遅れている果実を摘むことで、成熟のタイミングを揃えることができ、収穫作業の効率も良くなります。
摘果のタイミングと判断基準
摘果は、果実が肥大しはじめた直後〜直径2〜3cm程度の時期に行うのが理想です。あまり大きくなってからでは、株に無駄なエネルギーを使わせてしまい、逆効果となります。
どの果実を残すべきか?
摘果で重要なのは「残す実を決める」こと。以下のような基準をもとに選びます。
• 中心に位置し、形が良く、肥大が早い果実
• 変形していない果実(割れ、奇形がない)
• 虫や病気の被害がない健全な実
逆に、どの果実を摘むべきか?
• 肥大が遅れている実(他の実より小さい)
• 先端寄りや花房の外れにある実(栄養が届きにくい)
• 奇形果、傷果、虫害果
• 葉に隠れているなど、光が当たりにくい位置の実
例として、1段花房に7〜8果着果している場合、最終的に4果前後に絞るのが一般的です(高糖度栽培なら3果、収量重視なら5果程度まで可)。
摘果の実践方法とコツ
手か?ハサミか?
• 手でつまんで折る場合は、果梗を傷めないように注意。
• 確実に切るなら、清潔なハサミを使う方が安全です。(ウイルス病にかかっている場合は、ハサミから感染する場合があるのでNG!)
• 切り口から病原菌が入らないよう、雨天や高湿時の摘果は避けるのがベター。
一気にやらず、段階的に
いきなり全部の果実を間引くのではなく、2回に分けて少しずつ摘果することで、株にかかるストレスを減らせます。特に夏場は樹勢を見ながら調整するのがポイントです。
摘果の失敗例から学ぶ
• 欲張って全部の実を残したら、小さくて味の薄いトマトばかりに…
• 摘果を遅らせたら、株がバテて次の段に花がつかなくなった
• 摘みすぎてしまい、収穫量が大きく落ち込んだ
摘果に「正解」はありません。気温、日照、品種、株の勢いによって、最適解は日々変わっていきます。だからこそ大切なのは、「毎日の観察」です。よく見て、よく考え、タイミングを読み、ほんの少しだけ“勇気ある決断”を下す。その積み重ねが、味と収量の差となって現れます。

摘果は、単なる数合わせではありません。どの実を残すか――それは、栽培者が果実に与える「選ばれし使命」です。
仕立て・摘葉・摘果の応用と応急処置

〜自然と向き合い、対応する力〜
トマト栽培において「正解」は一つではありません。天候、気温、品種、栽培方法によって、仕立て・摘葉・摘果の“さじ加減”は日々変化します。どんなに理想的なマニュアルを持っていても、自然はその通りには動きません。だからこそ、経験と観察力に基づいた“応用力”と“応急対応”が、安定したトマトづくりに不可欠なのです。
異常気象や病害時の応用例
梅雨や長雨で病気が心配な時
• 摘葉を控えめに
湿気が多い時期は、葉を取りすぎると株の呼吸が乱れ、逆に病気の侵入口になることがあります。風通しは確保しつつ、最小限の摘葉にとどめ、病気の兆候がある葉だけを取り除く判断が重要です。
• 株元の風通しを確保
摘葉よりも「株元の整理(下葉の除去や支柱周りの整備)」を優先することで、病気のリスクを減らせます。
猛暑・乾燥時の対応
• 摘葉を減らし、葉を日傘代わりに
強烈な日差しによる「日焼け果(サンバーン)」を防ぐためには、葉をあえて残す判断が求められます。特に果実の上にかぶさる葉は、“日よけ”として残すのが鉄則です。
生育が旺盛すぎる(暴れ株)
• わき芽がどんどん出る/葉が大きくなる
窒素過多などで株が暴れる場合、わき芽の除去や摘葉をこまめに行い、樹勢を抑える方向へ調整します。また、過度な摘果は控え、株のエネルギーをうまく分散させましょう。
品種別に見る調整法の違い
トマトには、大玉、中玉、ミニなど様々な品種があり、それぞれ適した管理法があります。
大玉トマト
• 株がデリケートで、過剰な摘果・摘葉はリスク
• 花房1つあたり3〜4果に絞って、高品質を狙う
• 花房の直下の葉はなるべく残す
中玉・ミニトマト
• 生育旺盛なので、わき芽や葉の管理が重要
• 多段収穫が前提なので、仕立ては簡潔に
• 果実数が多いため、摘果は“整理”というより“バランス調整”の感覚
判断に迷ったときの「3つのチェックポイント」
1. 株の色を見る
濃すぎる→肥料過多・葉を整理/薄すぎる→光合成不足・葉は温存
2. 葉の触感と角度を確認
垂れている→水分ストレス/ピーンと立っている→元気・摘葉可能
3. 果実の肥大と色付き
肥大が止まっているなら、摘果が必要かも
着色が悪いなら、葉の整理を検討
応急処置で対応する力を養う
トマト栽培は自然との共同作業。台風、強風、雹、高温障害――予測不能な出来事も日常茶飯事です。そんな時に求められるのは、「まず観察し、次に仮説を立て、そしてやってみる」という実践的な思考です。
• 病気の兆候が出たらすぐに葉を切る
• 果実が割れ始めたら水管理を見直す
• 樹勢が落ちたら追肥ではなく「葉の整理」から試してみる

正しく育てるよりも、臨機応変に育てるという姿勢が、最終的な成功につながります。
手間を愛に変える、トマトとの対話

農業や家庭菜園で栽培するトマトは、人の手を必要とする作物です。仕立てて、葉を整え、実を選ぶ――その一つひとつの作業に、私たちのまなざしと意志が宿ります。時に迷い、時に失敗しながらも、トマトと向き合う日々の中に、静かで確かな“対話”が生まれます。
「このわき芽は残そうか、切ろうか」「この葉は、もう役目を終えただろうか」「この実は、栄養をもらえるだろうか」――そう問いかけながら手を動かす瞬間、そこには管理ではなく信頼関係があります。
トマトは正直です。手をかけたぶんだけ応えてくれるし、見過ごしたことも、きちんと実に現れます。だからこそ、愛情と観察力を持って向き合うことが、美味しい実を育てる最良の方法なのです。
仕立て・摘葉・摘果という三つの作業は、効率のための技術であると同時に、「育てる喜び」を感じるための道でもあります。

毎日の手間の中に、命の流れを感じ、自分自身のリズムを取り戻す。そんなトマト栽培の深さと面白さを、これからも楽しんでいきましょう。