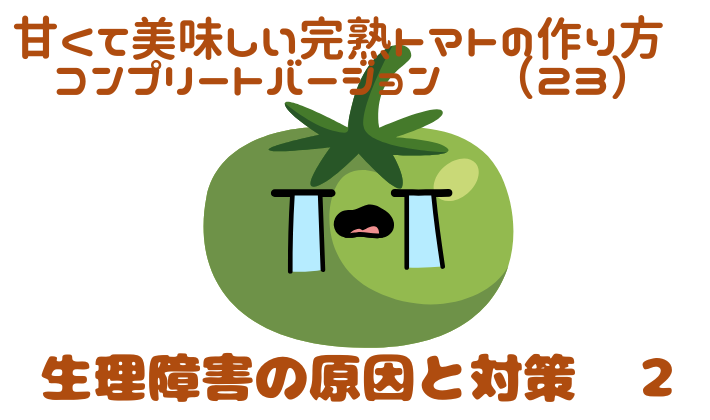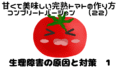イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方
前回の続きです。
葉・茎に現れる生理障害
トマトの健康状態は、葉や茎の様子にいち早く現れます。とくに葉色の変化、形の異常、茎の伸長などは、栄養状態や環境ストレスの“鏡”のような存在です。見落としがちな異常を正しく理解し、早期の対応に役立てましょう。
葉の縮れ・湾曲(葉巻き症状)
症状
葉が内側や上向きに巻き込むように変形し、しわや波打ちが見られます。特に新葉や生長点近くの葉でよく起こります。
原因
- 高温や強日射による蒸散過多
- 窒素過剰による草勢暴走
- 根の機能低下や乾燥ストレス
- マグネシウム欠乏による代謝異常
対策
- 換気や遮光で高温環境を和らげる
- 窒素施肥の量やタイミングを調整する
- 安定した潅水管理と排水性のよい土壌作り
- マグネシウム葉面散布で代謝補助
葉の黄化・クロロシス
症状
葉の緑が抜けて黄色くなり、とくに古い葉から進行します。葉脈だけが緑を保ち、葉脈間が黄色になる“葉脈間クロロシス”も典型例です。
原因
- マグネシウム、鉄、硫黄などの欠乏
- 過湿や根傷みによる吸収障害
- pHの上昇(アルカリ土壌)による微量要素の不溶化
- 酸素不足(根の窒息)
対策
- 土壌pHを6.0〜6.5に保つよう調整
- マグネシウム(苦土石灰)や鉄キレート剤の施用
- 根張りを改善し、過湿を避ける
- 肥料設計を見直し、微量要素を適切に補う
生長点の異常(芯止まり・わき芽異常)
症状
生長点の展開が止まり、芯が縮んだり変色します。新葉が変形・小型化し、わき芽が不規則に出ることもあります。
原因
- ホウ素欠乏
- 著しい低温ストレス(夜温10℃以下)
- 過湿による根の機能低下
- 高濃度の葉面散布や薬剤による薬害
対策
- ホウ素を含む微量要素資材の施用(0.1〜0.3ppm程度)
- 夜間の温度を確保する(特に育苗期)
- 葉面散布は適正濃度・タイミングを守る
- 土壌の排水性を高め、根環境を健全に
茎の徒長・軟弱化
症状
茎が間延びして細長くなり、節間が長く、葉が間引きされたようにまばらになります。倒伏や折れやすさも併発します。
原因
- 日照不足(曇天続きや密植)
- 窒素過多による草勢偏り
- 温度が高すぎる、または低すぎる場合
- 風通し不足や過繁茂
対策
- 光を確保するための適正な株間と摘葉
- 施肥量の見直し(特に窒素)
- ハウス内の温度・湿度管理
- ストレスを与えない草勢コントロール

葉や茎の異常は、トマトが“根本的に苦しんでいる”ことを教えてくれる大切な兆候です。見過ごされがちですが、初期の変化に敏感になることで、生育後半の果実品質を守ることができます。
次章では、花と着果に関する生理障害について、具体的な症状とともに解説します。
花と着果に関する生理障害
トマト栽培において「花が咲かない」「咲いても実がつかない」「実が奇形になる」といった症状は、生産者にとって大きな悩みの種です。これらは環境や栄養条件の影響を強く受ける「生理的障害」であり、栽培管理のあり方が直接反映されます。以下に代表的な症状と対策を詳しく解説します。
落花・落果
症状
花が咲いても果実がつかずにポロリと落ちてしまう、あるいは着果しても小さなうちに落果してしまう現象です。症状は1〜2段目の房で起きやすく、初期段階で発生すると収量に大きく響きます。
原因
- 高温(30℃以上)や低温(12℃以下)による花粉不活性
- ホルモンバランスの乱れ
- 過剰な草勢による生殖成長の抑制
- 水ストレス(潅水不足・急激な乾湿差)
対策
- 着果ホルモン(トマトトーン等)の使用(適正希釈で)
- 温度管理の徹底(夜温の確保と換気)
- 草勢のコントロール(窒素過多を避け、日照を確保)
- 潅水を安定させて根にストレスを与えない
奇形果(ネコ目果・裂開果)
症状
果実の形が不規則になったり、凹みができたり、果実先端に深い溝が入る「ネコ目果」などが生じます。見た目が悪く、商品価値が下がってしまいます。
原因
- 低温期の開花・受粉による花粉の異常
- ホウ素欠乏やホルモンの不均衡
- 花弁数の異常や重複花(多心花)の着果
- 強すぎる草勢や栄養バランスの偏り
対策
- 定植初期〜開花期の夜温管理(最低15℃程度を確保)
- ホウ素など微量要素の葉面散布(過剰注意)
- 着果数を絞って養分集中
- 生長点の安定管理と過剰な側枝の整理
着果不良・小果・種なし果
症状
果実が極端に小さくなったり、中に種が形成されない「種なし果」となったりします。開花しても十分に果実が肥大せず、房全体の収穫量が減ってしまいます。
原因
- 花粉の形成不良(高温・低温・乾燥)
- 着果数の過多による負担分散
- カリ・ホウ素不足
- 花粉の寿命の短さ(特に乾燥条件下)
対策
- カリ肥料を十分に施し、果実肥大を促す
- 高温・乾燥期には花房へのミスト散布や遮光
- 株あたりの着果数を適正に制限(摘果・わき芽整理)
- 交配補助(人工授粉)やホルモン処理の活用
花数が少ない・咲かない
症状
花房の発達が悪く、蕾が小さい、もしくは花そのものがつかない現象です。特に初期の段数で発生すると、その後の成長にも影響します。
原因
- 草勢が強すぎて栄養成長に偏る
- 窒素過多
- 光不足(曇天続き、過繁茂)
- 高温・低温の繰り返しによる花芽分化不良
対策
- 適正な施肥管理(特に窒素の抑制)
- 日照を確保するための摘葉や枝整理
- 生長点周囲の温度環境を安定させる
- 株のバランスを整えるための着果制限や摘心調整

花や果実の問題は、「トマトが子どもを残せない状態」にあるというサインです。これは一時的な環境異常だけでなく、栽培設計全体の見直しを促しているとも言えます。
症状に表れたトマトからのサインを的確にキャッチし、健全な着果と果実肥大へと導くことが、安定した収量への鍵となります。
次章では、トマトの根に起因する生理障害について解説します。根は植物の生命線。そのトラブルは全身に波及します。
根に起因する生理障害
トマトの根は、まさに「見えない生命線」です。水と養分を吸収し、植物全体の生育と果実の品質を左右する重要な器官です。しかし、根の不調は目に見えにくいため、症状が地上部に現れるころにはすでに深刻化していることもあります。ここでは、根に起因する代表的な生理障害を取り上げ、その特徴と対策を解説します。
根腐れ・根の発達不良
症状
株全体の生育が鈍化し、葉が萎れたり、下葉から黄化・脱落するようになります。果実も肥大せず、品質が著しく低下します。根を掘り上げてみると、細根が黒く変色し、腐敗していることがあります。
原因
- 過湿(排水不良)、酸素不足による根の窒息
- 高温期の根傷み
- 塩類集積による根の機能低下(EC過多)
- 土壌pHの異常や老廃物の蓄積
対策
- 畝の高く設計・深耕・排水性の良い用土使用
- 太陽熱消毒や土壌改良(有機物・微生物資材の投入)
- 塩類濃度(EC)をチェックし、過剰施肥を避ける
- 潅水を浅く・回数多めにして根に酸素を与える
- 定期的に土壌診断を実施し、pHや栄養バランスを調整
根頭肥大(ゴボウ根化)
症状
根の先端が膨らんで「コブ状」になり、まっすぐ伸びず、吸収力が著しく低下します。新しい根が出にくくなり、株全体の生育が弱々しくなります。
原因
- 苗の移植時に根が折れる・乾燥する
- 定植後に潅水不足で根が伸びない
- 固結土や物理性の悪い土壌による根の障害
- 窒素過多による根の組織異常
対策
- 苗定植時は根鉢を崩さず、根を傷つけない
- 定植直後にたっぷり潅水して活着を促進
- ふかふかの団粒構造を作るために腐植や堆肥を投入
- 初期の施肥量を控えめにして、根の探索性を高める
根の老化・根量不足
症状
栽培後半になると、急激に下葉が黄化・脱落し、草勢が落ちて果実肥大が止まってしまうことがあります。根を見てみると、白根が少なく茶色く老化している状態です。
原因
- 長期間の連続着果による根への過負荷
- 栄養や水の不足による根の消耗
- 炎天下での高温障害(特に地温35℃以上)
- 連作による土壌の疲弊と病原菌の蓄積
対策
- 栽培中盤に根を若返らせるよう、潅水と肥料を調整
- 通気性と保水性を兼ねた用土を選ぶ
- 夏場はマルチや遮熱資材で地温を下げる
- 土壌改良材や微生物資材で根圏環境を活性化
- 輪作や太陽熱処理で土壌のリフレッシュを行う
根毛の減少・機能低下
症状
一見、根の量はあるように見えても、水や肥料をうまく吸えず、生育が止まることがあります。よく見ると、細かい根毛(吸収根)がほとんど存在せず、根が働いていない状態です。
原因
- 低温や高湿により根の活動が低下
- 根傷み(肥料焼け、薬害、酸素不足)
- 病原菌の感染初期(根腐病などの前段階)
対策
- 土壌温度を確保(15℃以上が理想)
- 施肥と潅水を穏やかに調整し、根の刺激を減らす
- 活力資材(海藻エキス、フミン酸など)で根の再生を促す
- 軽症段階なら、養分より「環境整備」が効果的

根の問題は「地下の見えないストレス」が原因であることが多く、放置すれば地上部全体に影響が及びます。根を診るためには、時に土を掘って観察する習慣が必要です。
トマトにとって心地よい土壌を整えることこそが、あらゆる障害の予防につながる第一歩です。
次章では、トマトに必要な栄養素の過不足によって引き起こされる「要素欠乏・過剰」による生理障害を整理し、対策を表形式でわかりやすくご紹介します。
要素欠乏・過剰による症状と対策
トマトが健康に育つためには、窒素(N)やリン(P)、カリウム(K)といった三大要素だけでなく、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、微量要素(ホウ素、鉄、亜鉛など)もバランスよく必要です。
栄養素は「多すぎても少なすぎても」植物にとってはストレスとなり、生理障害の原因になります。
ここでは、よく見られる要素欠乏・過剰の症状と対策をまとめます。
三大要素(N・P・K)
| 要素 | 欠乏症状 | 過剰症状 | 主な対策 |
| 窒素(N) | 全体に黄化、下葉から進行、葉が小さくなる、生育不良 | 葉が濃緑、過繁茂、果実の肥大・着色が遅れる | 欠乏時:早めの追肥、過剰時:灌水による塩類洗い流し・施肥停止 |
| リン(P) | 葉が紫がかる、節間短く、花付きが悪い | Zn欠乏を誘発、根の過成長・微量要素吸収阻害 | 初期にしっかり施肥、土壌pH6.0~6.5を保つ |
| カリ(K) | 葉の縁から褐変(縁枯れ)、空洞果、小玉果 | Ca・Mgの吸収を妨げる、葉が焼ける | 欠乏時:速効性カリ資材、過剰時:他要素補給でバランス調整 |
二次要素(Ca・Mg・S)
| 要素 | 欠乏症状 | 過剰症状 | 主な対策 |
| カルシウム(Ca) | 尻腐れ果、芯腐れ果、新葉の萎縮・変形 | MgやKの吸収障害、塩類集積による根傷み | 葉面散布やCa入り資材、潅水の安定 |
| マグネシウム(Mg) | 葉脈間クロロシス、下葉から黄化 | Ca吸収を妨げ、草勢乱れ | Mg補給(苦土石灰や葉面散布)、Caとのバランスに注意 |
| 硫黄(S) | 葉の全体が淡黄化、新葉も黄色くなる | まれ(強い酸性化で根にダメージ) | 有機質肥料や硫酸系肥料を使って補給 |
微量要素(B・Fe・Mn・Znなど)
| 要素 | 欠乏症状 | 主な対策 |
| ホウ素(B) | 芯止まり、奇形果、花落ち、わき芽異常 | 葉面散布(0.02~0.05%)、過剰は毒性注意 |
| 鉄(Fe) | 新葉の黄化(葉脈は緑)、生育停滞 | キレート鉄の施用、pH調整で吸収改善 |
| マンガン(Mn) | 葉に小斑点、クロロシス、新葉の異常 | キレートMn資材で補給、過剰施用は避ける |
| 亜鉛(Zn) | 小葉化、わき芽異常、葉が狭くなる | 土壌にZn含有資材を混和、石灰の多用は避ける |
実践的な対処のポイント
- ①症状の出る位置を観察する
下葉:N、Mg、Kの欠乏が多い
新葉:Ca、Fe、Bなど移動性が低い要素の欠乏が多い - ②土壌のpHとECを測定する
適正pH(6.0〜6.5)、EC過多(塩害)は吸収障害の原因に - ③単独の要素だけで判断しない
欠乏・過剰は連鎖する。例:K過多→Ca吸収阻害→尻腐れ果 - ④葉面散布は「薄く・こまめに」
濃すぎると薬害や果面のシミに。希釈倍率と時間帯に注意

症状はトマトからの“栄養設計の見直し要請”とも言えます。表面だけでなく根本から見直すことで、より安定した生育と収量を得ることができるでしょう。
次はいよいよ最終章、トマトの生理障害と向き合ううえで最も重要な「予防的視点」についてお話しします。
生理障害への“予防的思考”を持とう
これまで見てきたように、トマトに現れるさまざまな生理障害には、それぞれ明確な原因と対策があります。しかし本当に大切なのは、症状が出てから慌てて対処するのではなく、未然に防ぐための予防的思考を持つことです。
生理障害は、病気や害虫と違って薬剤で治すことができません。環境条件や栄養バランス、土壌の状態といった「栽培管理の結果」として現れるため、作物自身が環境の歪みを体で表現しているとも言えるでしょう。
そのためには、日々の観察こそが最も重要な予防策です。
「見る」ではなく「診る」
トマトの様子をただ眺めるのではなく、「何が起きているのか?」を意識して観察することが大切です。
たとえば:
- 葉が巻いている → 高温?肥料過多?根傷み?
- 果実の尻が黒い → Ca不足?潅水不安定?
- 花が落ちる → 草勢強すぎ?温度異常?
このように「なぜ?」と問いながら診ることで、障害の前兆をつかむことができます。
環境を整えることは、トマトへの思いやり
トマトは本来、とても正直な植物です。
光、水、風、温度、養分、根の環境――それらが整えば、自然と健康に育ち、障害も起きにくくなります。
言い換えれば、生理障害とは、栽培環境からの警告サインでもあるのです。
だからこそ、
- 土作りを丁寧に行う
- 肥料を「与える」より「効かせる」意識を持つ
- 光と風が通る草姿を保つ
- 栽培記録をつけて「勘」ではなく「根拠」で判断する
これらの積み重ねが、障害を防ぐ最大の武器になります。
“共に生きる”という感覚を忘れずに
トマト栽培は、単なる農作業ではなく、自然との共同作業であり、命との対話です。
生理障害に出会ったとき、「なぜこんなことに……」と嘆くよりも、「何を教えてくれているのか?」と受け止めることで、栽培者としての感性が磨かれていきます。
トマトが元気に育つことは、私たち自身の在り方を映す鏡でもあります。
自然とともに歩むその姿勢の中にこそ、安定した収穫と喜びが生まれるのではないでしょうか。
トマトは、あなたの手の中にある小さな宇宙です。

生理障害というサインを通じて、トマトの声に耳を傾けながら、これからも一歩ずつ、よりよい栽培を重ねていきましょう。