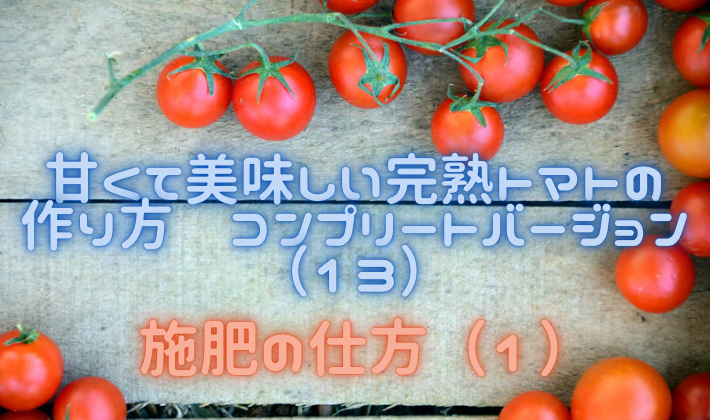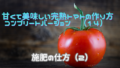イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方
イマジンファーム・アップルトマトのあるスギです。
今日は1月27日です。1年で最も寒い時期です。
大玉トマト「桃太郎ファイト」の収穫も1月中旬から始まり、徐々に収量も増えてきました。甘さもコクもしっかりあり、味的には合格点です。
昨年の秋深くまで暑さが続いた影響で弱っていた株も、元気な新芽が出て来てなんとか回復して来ました。収穫開始時期が2か月ほど遅れそうです。
農業はいくらやってみても、思い通りには行きません。それがまた楽しく、やり甲斐があるのですが。
大玉トマトに樹勢が弱っている株が多かったので、なんとか復活させようと思い、HB101を週1回、灌水時に5000倍に薄めて流しました。
昔、何度か使っていた事があったのですが、結構、価格が高いので使うのを控えていました。
1週間目はあまり効果がなかったのですが、2週間目から脇芽が顔を見せ始めてきて、3週間目には、勢いの良い脇芽があちこちから出て来ました。
HB101を流したハウスと流さなかったハウスでは、樹勢の弱かった株の回復の勢いが断然違いました。
いろんな植物活性剤がありますが、HB101は、確実に効果が出る数少ない資材の一つだと思います。
冬場はトマトの生育が弱りやすいので、定期的にHB101を使用して冬を乗り越えて行こうと思います。

今回は肥料の施肥の仕方、肥料の種類や特徴について書いていきたいと思います。
基本事項
私が行なっている栽培方法は養液土耕栽培です。肥料は化学肥料(無機肥料)を使用して、有機肥料は一切使用していません。
肥料は養液栽培用肥料を自分で配合して液肥を作ります。
基本、肥料は必要最低限の量だけを施肥します。トマトの要求量に合わせて過不足なく供給する。
肥料が多いとトマトが過剰に吸って株が暴れて管理しにくくなるし、軟弱に育ったトマトは病害虫の被害を受けやすくなります。
私が基本としている液肥の濃度はEC0,6mS/cmです。葉色が薄かったり、樹勢が弱い場合はEC1,0mS/cmまで高めます。
EC(Electrical Conductivity)とは、培養液に含まれる肥料濃度を示す値で、「電気伝導度」といいます。培養液中の全溶質の濃度を表し、溶けているイオンの量が多いほどEC値が高くなります。
生育ステージ、季節の変化、天候の変化、樹勢の強弱など、日々変化するトマトの状態に合わせて施肥する。
収穫終了時には土中の肥料分がほぼ無い状態にもっていく。
肥料のやり過ぎは厳禁です。トマトに障害が出るのももちろんですが、土中に肥料分が蓄積して、良質なトマトができなくなります。
また、肥料を過剰に流し、廃液が農場の外に流れ出す事で、環境汚染にも繋がります。

肥料はトマトの生育を見ながら、適量を与えるようにしましょう。
化学肥料(無機肥料)の利点
1. 即効性がある
– 無機肥料は、栄養素が植物に直接吸収されやすい形で含まれています。これにより、植物が速やかに必要な栄養を吸収でき、生育を早める効果が期待できます。
2. 成分の均一性と正確な配合
– 無機肥料は、窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)などの含有量が正確に調整されています。これにより、土壌の状態や作物のニーズに合わせて必要な量を計画的に与えることができます。
– 一方、有機肥料は成分が一定でない場合があり、施肥量の調整が難しいことがあります。
3. 施肥量とタイミングのコントロールが容易
– 無機肥料は特定の時期や条件に合わせて適切な量を与えることで、作物の生育を計画的に管理できます。
– また、必要な成分を必要な時期に集中して供給することが可能で、肥料効率が高いと言えます。
4. コストパフォーマンスが高い場合がある
– 化学肥料は大量生産されるため、特に大規模な農業ではコストが抑えられやすいです。
– また、作物の収量や品質を短期間で向上させられるため、経済的メリットが期待できます。
5. 土壌中での分解を必要としない
– 有機肥料は微生物による分解を経て植物に吸収されますが、この過程には時間がかかり、分解が十分でない場合は効果が出にくいことがあります。一方、無機肥料は施肥後すぐに効果を発揮します。
6. 害虫や病原菌のリスクが少ない
– 有機肥料は動植物由来の材料を含むため、不適切な処理によって害虫や病原菌を引き起こす可能性があります。無機肥料はそのようなリスクが低く、衛生的です。

化学肥料は即効性があって、使いやすいので緻密で栽培状況に沿った施肥管理ができます。
化学肥料(無機肥料)の欠点
1,土壌の劣化
– 微生物の減少
無機肥料は有機物を含まないため、土壌中の微生物を活性化する効果が少なく、長期的には土壌の健康を損なう可能性があります。
– 土壌の酸性化
長期間使用すると、特にアンモニウム系窒素肥料の影響で土壌が酸性化しやすくなり、土壌の肥沃度が低下します。
2,環境への悪影響
– 地下水汚染
硝酸態窒素などが地下水に浸透すると、水質汚染を引き起こし、飲料水の安全性を損なうリスクがあります。
– 肥料成分の流出
過剰施肥により、窒素やリンが雨水とともに河川や湖に流れ込み、富栄養化を引き起こします。これが藻類の異常繁殖(アオコの発生)や生態系の破壊につながることがあります。
3,施肥過多による作物への悪影響
– 無機肥料を過剰に使用すると、塩類濃度が高くなり、植物の根が吸水できなくなる「塩害」が発生する可能性があります。
– 過剰な栄養供給は、徒長(茎や葉が必要以上に伸びる)や病害虫の発生リスクを高めることがあります。
4, 有機質の不足
– 有機肥料と違い、有機質を補充する効果がないため、土壌の団粒構造(通気性・排水性が良い状態)を維持できません。これにより、土壌が硬化し、保水力や通気性が低下することがあります。
解決策
これらの欠点を軽減するために、以下のような取り組みが推奨されています
– 適切な施肥計画:作物のニーズに基づいた施肥量やタイミングの管理。
– 土壌診断の実施:施肥量を最適化し、過剰施肥を防ぐ。
無機肥料の利点を活かしつつ、環境と作物の両方に配慮したバランスの取れた農業が重要です。

最近、肥料は急激に価格高騰してきているので、計画的に無駄なく使用して経費削減していきましょう。
トマト栽培に必要な肥料分(無機養分)
多量要素
窒素、リン酸、カリ、カルシウム、マグネシウム、硫黄
微量要素
鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン
肥料(多量要素)の各種養分吸収量
窒素を100とするとリン酸26、カリ180、カルシウム74、マグネシウム18。
カリの吸収量が多く、リン酸、マグネシウムの吸収量は窒素の1/3以下です。

トマトの養分吸収量に見合った肥料を与えることが、健全な株を作り、甘くて美味しい果実の収穫へと繋がります。
肥料(多量要素)の特徴
トマト栽培で使用する主成分の肥料、窒素、リン酸、カリ、カルシウム、マグネシウム、硫黄の特徴を詳しく述べていきます。
窒素
窒素の役割
– 葉緑体(クロロフィル)の構成要素
窒素はクロロフィルの主要成分で、光合成を促進します。トマトの葉の健康状態と成長に直接影響を与えます。
– タンパク質の生成
窒素はアミノ酸やタンパク質の合成に必要です。これにより、トマトの成長や代謝が活発化します。
– 細胞分裂と成長の促進
核酸(DNAやRNA)の構成要素であるため、新しい細胞の形成や成長に寄与します。
窒素不足の影響
– 葉が黄色くなる(黄化)
特に古い葉から症状が進行します。これは窒素が移動可能な養分であり、新しい葉に優先的に供給されるためです。
– 成長の遅延
葉、茎、果実の成長が遅くなり、トマトの全体的な生産性が低下します。
– 果実のサイズ縮小
十分な窒素が供給されないと、果実が小さくなる傾向があります。
窒素過剰の影響
– 茂りすぎた葉や茎
葉や茎が異常に成長し、果実の発育が遅れることがあります(樹ボケ)。
– 花や果実の数の減少
窒素過剰により、トマトのエネルギーが葉や茎の成長に使われ、花や果実が減少します。
– 病害虫への感受性の増加
過剰な窒素は細胞が軟弱化し、病害虫に攻撃されやすくなることがあります。
– 果実品質の低下
糖度が下がり、水っぽい果実になることがあります。
適切な窒素管理
– 生育ステージに応じた窒素供給
トマトの初期成長段階では窒素が多めに必要ですが、開花期や果実肥大期には過剰な窒素を避け、リン酸やカリウムを重視する必要があります。
適切な窒素供給を行えば、トマトの葉が鮮やかな緑色を保ち、健全な成長と高品質の果実収穫につながります。
リン
リン酸の役割
– エネルギー供給
リン酸はATP(アデノシン三リン酸)の構成成分で、植物のエネルギー代謝に不可欠です。これにより、光合成や養分の吸収・運搬が効率化します。
– 根の発育促進
リン酸は根の成長を促進し、土壌中から水分や栄養素を吸収する能力を高めます。特に初期生育段階では、健康な根系の発達に重要です。
– 花や果実の形成
リン酸は花芽の形成を助け、果実の着果率を向上させます。また、果実の成熟を促進し、品質の良い収穫物を得るために重要です。
– 病害耐性の向上
リン酸は細胞膜を強化し、病害虫への耐性を高める効果があります。
リン酸不足の影響
– 葉の変色
葉が暗緑色から紫色や赤色に変わることがあります。これは、葉にアントシアニンが蓄積されるためです。
– 成長の遅延
全体的な成長が鈍くなり、茎や根が発育不良になることがあります。
– 花や果実の形成不良
花の数が減少し、着果率が低下します。また、果実の成熟が遅れることがあります。
– 根の発達不良
根系が弱くなり、養分や水分の吸収が制限されるため、全体の生育に悪影響を及ぼします。
リン酸過剰の影響
– 他の栄養素の吸収阻害
リン酸過剰は鉄(Fe)、亜鉛(Zn)、マグネシウム(Mg)などの吸収を妨げ、欠乏症を引き起こす可能性があります。
– 根の成長の抑制
リン酸濃度が高すぎると、逆に根の発育が阻害されることがあります。
適切なリン酸管理
– 土壌のpHを適正化
リン酸は中性付近のpH(6.0~7.0)で吸収されやすいため、土壌pHを調整することが重要です。
– 適切な施肥量
リン酸は施肥しすぎると土壌に蓄積されやすいため、土壌診断を行い必要量だけを施肥します。
– 育成段階に応じた供給
トマトの生育全期間にわたって供給し、開花・果実肥大期に入ると徐々に多くしていきます。
リン酸が果実品質に与える影響
– 果実の糖度が高まり、味が良くなる。
– 色づきが均一で鮮やかになる。
– 果実が硬くなり、輸送性や保存性が向上する。
リン酸はトマトの成長、開花、果実の品質に不可欠な要素であり、特に初期生育と果実形成において大きな影響を与えます。適切な量とタイミングでリン酸を供給することで、健全な生育と高品質な収穫が可能になります。
カリ
カリの役割
(1) 光合成とエネルギー代謝の促進
カリウムは光合成を効率化し、生成された糖をエネルギー源として植物全体に分配します。
(2) 浸透圧の調整
カリウムは細胞内の浸透圧を調整し、水分吸収と蒸散を制御します。これにより、トマトの耐乾性が向上し、葉や果実の品質が改善されます。
(3) 酵素活性の調整
カリウムは数百種類の酵素を活性化し、代謝を円滑に進めます。これにより、成長速度や果実の発育が促進されます。
(4) 病害耐性の向上
カリウムは細胞壁を強化し、病害やストレスに対する耐性を向上させます。
(5) 果実品質の向上
糖度の向上、果実の硬さや色づきの改善、貯蔵性の向上など、収穫物の品質全般に寄与します。
カリ不足の影響
(1) 葉の変色と縮れ
– 葉の縁が黄色くなり、次第に褐色の斑点が生じます(縁枯れ症状)。
– 古い葉から症状が進行します。
(2) 成長の停滞
– 茎が細くなり、全体的な成長が鈍化します。
– 果実の肥大が不十分になることがあります。
(3) 果実品質の低下
– 糖度が低下し、味が薄くなります。
– 果実が柔らかくなり、輸送性や保存性が悪化します。
(4) 病害や環境ストレスへの弱さ
– 病害虫への耐性が低下し、乾燥や高温に弱くなります。
カリ過剰の影響
(1) 他の栄養素の吸収阻害
– カリウム過剰はカルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)の吸収を妨げ、欠乏症を引き起こします。
– これにより、果実の尻腐れ症(カルシウム不足が原因)などの障害が発生する可能性があります。
(2) 土壌の塩類濃度の上昇
– カリウム肥料を多用すると土壌中の塩類濃度が高まり、根の発育を阻害することがあります。
カリの適切な管理
(1) 生育段階に応じた施肥
– 初期生育期:根や茎葉の成長を助けるために適量を供給します。
– 開花・果実肥大期:特に果実の品質向上に必要なため、十分な量を施します。
(2) バランス施肥
– カリウムだけでなく、窒素(N)やリン(P)など他の栄養素とのバランスを保つことが重要です。
(3) 葉面散布の活用
– 葉面散布による補給は効果的です。
カリが果実品質に与える影響
– 糖度の向上
果実に甘みを与え、風味が良くなる。
– 硬さと鮮度の維持
果実がしっかりし、輸送性や貯蔵性が高まる。
– 色づきの改善
鮮やかな赤色が得られ、市場価値が向上する。
カリウムはトマトの生育全般、特に果実の品質向上に欠かせない栄養素です。適切なタイミングと量で施肥を行い、他の栄養素とのバランスを保つことで、高品質なトマトを生産することができます。
カルシウム
カルシウムの役割
(1) 細胞壁の強化
– カルシウムは細胞壁の構成成分で、ペクチンと結合して細胞壁を強化します。これにより、植物全体の構造が安定します。
(2) 細胞の分裂と拡大の促進
– 細胞分裂や新しい細胞の拡大に必要で、特に新芽や果実の成長に影響を与えます。
(3) 病害耐性の向上
– 細胞壁が強化されることで病原菌や害虫への抵抗力が高まり、植物の健康状態が改善されます。
(4) 水分管理のサポート
– カルシウムは細胞膜の透過性を調整し、水分の移動を助けます。これにより、植物内の水分バランスが保たれます。
カルシウム不足の影響
(1) 果実の尻腐れ症
– トマトの果実の底部が黒く腐る障害(尻腐れ症)はカルシウム不足の典型的な症状です。これは、カルシウムが果実に十分供給されないため、細胞壁が弱くなることが原因です。
(2) 成長点の障害
– 新芽や若葉が変形したり、成長が止まったりします。
(3) 葉の異常
– 古い葉ではなく、新しい葉に症状が出やすく、葉がカールしたり、色が薄くなったりすることがあります。
(4) 果実の品質低下
– 果実が柔らかくなり、裂果や保存性の低下が起こることがあります。
カルシウム過剰の影響
(1) 他の栄養素の吸収阻害
– カルシウム過剰はマグネシウム(Mg)やカリウム(K)の吸収を妨げ、欠乏症を引き起こす可能性があります。
(2) 土壌のpH上昇
– 過剰なカルシウム供給は土壌pHを上昇させ、他の栄養素の利用効率を低下させることがあります。
適切なカルシウム管理
カルシウムは植物体内で移動性が低いため、適切な管理が重要です。以下の方法で供給を最適化できます。
(1) 土壌のpH調整
– トマトは中性付近(pH 6.0~7.0)の土壌でカルシウムを吸収しやすいため、pHを適切に調整します。
(2) 施肥の工夫
– 成長期には葉面散布でカルシウムを補給する方法も効果的です。
(3) 水分管理
– 土壌が乾燥しすぎるとカルシウムが吸収されにくくなるため、適切な灌水を行います。
(4) 根の健康維持
– 健康な根を維持することで、カルシウムを効率的に吸収できます。有機物や微生物を活用して土壌環境を整えます。
カルシウムが果実品質に与える影響
– 果実の硬さと鮮度の維持
保存性が向上し、輸送中の損傷が減少します。
– 裂果の予防
果実が丈夫になり、裂果の発生を抑えます。
– 味と外観の改善
果実が均一に成熟し、外観が良くなるとともに、食味が向上します。
カルシウムはトマトの成長、病害耐性、果実品質に不可欠な栄養素です。特に果実の尻腐れ症を防ぐためには、適切な供給と管理が重要です。土壌診断や水分管理を組み合わせてバランス良くカルシウムを供給することで、トマトの健全な生育と高品質な収穫が可能になります。
マグネシウム
マグネシウムの役割
(1) クロロフィル(葉緑素)の構成成分
– マグネシウムはクロロフィルの中心金属であり、植物が光合成を行うために不可欠です。
– 光エネルギーを化学エネルギーに変換し、成長に必要な糖やエネルギーを供給します。
(2) 酵素反応の活性化
– マグネシウムは多くの酵素を活性化し、エネルギー代謝やデンプン・タンパク質の合成をサポートします。
(3) 栄養素の運搬
– マグネシウムは植物体内で糖や他の栄養素を運搬する働きを持ち、根や果実などの成長部位にエネルギーを供給します。
(4) 細胞膜の安定化
– 細胞膜の構造を安定化し、植物の健康を保つ助けをします。
マグネシウム不足の影響
(1) 葉の変色(葉脈間クロロシス)
– 古い葉で、葉脈の間が黄色くなり(クロロシス)、進行すると葉全体が枯れます。
– 葉脈が緑のまま残るのが特徴的です。
(2) 光合成の低下
– クロロフィルが減少するため光合成能力が低下し、全体的な成長が鈍くなります。
(3) 果実の品質低下
– 十分なエネルギー供給が行われないため、果実の肥大や糖度が不十分になります。
(4) 病害や環境ストレスへの弱さ
– マグネシウム不足は植物全体の活力を低下させ、病害虫や環境ストレスに対して弱くなります。
マグネシウム過剰の影響
(1) カルシウムやカリウムの吸収阻害
– マグネシウムが過剰になると、カルシウム(Ca)やカリウム(K)の吸収が妨げられ、欠乏症を引き起こします。
(2) 塩類濃度の上昇
– 土壌中の塩類濃度が高まり、根の発育を妨げることがあります。
マグネシウムの適切な管理
(1) 施肥の工夫
– 土壌pHを中性~やや酸性(pH 6.0~7.0)に調整することで、マグネシウムの吸収効率を高めます。
– 育成段階に応じた供給
トマトの生育全期間にわたって供給し、開花・果実肥大期に入ると徐々に多くしていきます。
(2) 葉面散布
– マグネシウム不足が見られる場合、硫酸マグネシウムを葉面散布することで迅速に補うことができます。
(3) 水分管理
– 過剰な乾燥や湿潤を避けることで、根の健康を保ち、マグネシウムの吸収を助けます。
(4) 他の栄養素とのバランス
– マグネシウム、カルシウム、カリウムのバランスを保つことで、欠乏症や過剰症を防ぎます。
マグネシウムが果実品質に与える影響
– 糖度の向上
光合成が促進されることで、果実の糖度が高まり、風味が良くなります。
– 鮮やかな色づき
果実の色づきが均一で鮮やかになります。
– 果実の肥大促進
十分なエネルギー供給により、果実が大きく育ちます。
マグネシウムはトマトの成長や果実の品質向上に欠かせない栄養素です。不足すると光合成や栄養素運搬に障害が出るため、土壌診断や適切な施肥管理を通じて、バランスよく供給することが重要です。特に、他の栄養素とのバランスを考慮した管理が、高品質なトマト生産につながります。
硫黄
硫黄の役割
(1) アミノ酸の構成成分
– 硫黄はシステインやメチオニンといった含硫アミノ酸の構成成分であり、これらはタンパク質の基礎を形成します。
– タンパク質の合成に不可欠で、細胞の成長や新陳代謝を促進します。
(2) 酵素活性の向上
– 硫黄は多くの酵素の活性化因子として働き、植物の代謝反応を助けます。
(3) クロロフィル合成のサポート
– 硫黄はクロロフィルの合成を助け、光合成の効率を向上させます。
(4) 植物の防御機構
– 硫黄を含む化合物(グルコシノレートなど)は、病害虫に対する植物の防御に寄与します。
(5) 香りと味の向上
– 硫黄は果実の風味や香りを改善し、トマトの品質を高めます。
硫黄不足の影響
(1) 葉の黄化(クロロシス)
– 硫黄不足では新しい葉が黄色くなる傾向があります(窒素不足の場合は古い葉が黄化します)。
– 特に若葉が薄黄色になり、光合成能力が低下します。
(2) 成長の遅延
– タンパク質合成が妨げられ、全体的な成長が鈍くなります。
(3) 果実の品質低下
– 果実のサイズや糖度が減少し、味や風味が劣化します。
(4) 収量の減少
– 光合成効率や栄養素の輸送が悪化するため、収量が減少します。
硫黄過剰の影響
(1) 土壌酸性化
– 硫黄過剰は土壌を酸性化させ、他の栄養素(特にカルシウムやマグネシウム)の吸収を妨げることがあります。
(2) 塩類濃度の上昇
– 硫酸塩の形で過剰に存在すると、塩害を引き起こすことがあります。
硫黄の適切な管理
(1) 施肥の工夫
– 硫酸マグネシウムや硫酸アンモニウムなどの肥料を使用して、適切な量の硫黄を供給します。
– 土壌中に有機物を添加すると、微生物の働きで硫黄が供給されやすくなります。
硫黄が果実品質に与える影響
– 糖度の向上
光合成が促進され、果実の糖度が増します。
– 香りと風味の強化
硫黄化合物が果実に独特の香りと深い味わいを与えます。
– 果実の大きさと色づきの改善
硫黄は果実の均一な成長と鮮やかな色づきを助けます。
硫黄はトマトの生育において、タンパク質合成、光合成、そして果実の品質向上に不可欠な役割を果たします。不足すると生育不良や品質低下を引き起こすため、適切な供給が重要です。土壌診断や施肥計画を通じて、他の栄養素とのバランスを考慮した硫黄管理を行うことで、健全なトマトの成長と高品質な収穫が可能になります。

多量要素はトマトの主となる大事な栄養素です。生育ステージに合わせた施肥管理をしっかりして、栄養の過不足のない丈夫なトマトを作っていきましょう。
微量要素の特徴
トマト栽培における微量要素(鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン)は、少量であっても重要な役割を果たし、植物の健康と収量に大きく影響を与えます。それぞれの特徴や役割を以下に説明します。
鉄(Fe)
役割
– クロロフィル(葉緑素)の合成
鉄はクロロフィル合成に必要で、光合成を支えます。
– 酵素の構成要素
酸化還元反応に関与する酵素や電子伝達系で重要な役割を果たします。
鉄不足の影響
– 葉の黄化(特に新葉で顕著)。
– 光合成が低下し、生育が鈍化します。
対策
– 鉄キレート剤を施肥したり、葉面散布で補います。
– 土壌pHを適切な範囲(pH 6.0~7.0)に調整して吸収を改善します。
マンガン(Mn)
役割
– 酵素活性の促進
光合成や窒素代謝に関与する酵素を活性化します。
– 活性酸素の除去
抗酸化作用を持つ酵素の構成要素です。
マンガン不足の影響
– 葉の黄化(鉄不足と似た症状で、新葉が特に影響を受けます)。
– 光合成や窒素代謝が低下します。
対策
– 硫酸マンガンを施肥する。
– 土壌が高pHの場合、酸性化剤を用いて吸収を促進します。
ホウ素(B)
役割
– 細胞壁の形成
細胞壁の構造を安定化し、細胞分裂を助けます。
– 果実の成長と品質向上
受粉・果実形成を支え、果実のサイズや品質に影響します。
ホウ素不足の影響
– 果実の奇形や割れ
トマトの果実が変形しやすくなる。
– 茎や根の成長障害
根が短くなり、茎が脆くなります。
対策
– ホウ砂(ホウ酸ナトリウム)を土壌または葉面散布で補給。
– 過剰施用による毒性を避けるため、適量を守ります。
銅(Cu)
役割
– 酵素反応の触媒
植物の呼吸やリグニン(木質)の合成を助けます。
– 病害抵抗性の向上
細胞壁を強化し、病害に対する防御を高めます。
銅不足の影響
– 葉の縮れや変色(若葉が影響を受ける)。
– 花や果実の形成が不良になります。
対策
– 銅製剤(硫酸銅など)を土壌または葉面散布で施用。
– 銅の過剰施用は毒性を引き起こすため注意が必要です。
亜鉛(Zn)
役割
– 酵素の構成要素
酵素の活性化やDNA・RNAの合成を助けます。
– ホルモン合成
オーキシン(成長ホルモン)の合成を促進します。
亜鉛不足の影響
– 葉の小型化と黄化(新葉で発生)。
– 節間が短くなり、全体の成長が鈍化します。
対策
– 硫酸亜鉛を施肥または葉面散布で補います。
– 土壌の高pHやリン酸過多を避けることで吸収を改善します。
モリブデン(Mo)
役割
– 窒素固定と代謝
窒素をアンモニウムや硝酸に変換する酵素に必要です。
– 酵素の活性化
硝酸還元酵素の構成要素として働きます。
モリブデン不足の影響
– 葉が黄色くなる(特に古い葉)。
– 窒素利用効率が低下し、植物が弱ります。
対策
– モリブデン酸ナトリウムを施肥。
– 土壌が酸性の場合、pHを中性に近づけて吸収を改善します。
微量要素はトマトの成長、病害抵抗性、果実品質に大きな影響を与えます。それぞれの役割を理解し、適切な管理を行うことで、健全な植物の成長と高品質な果実の生産をサポートできます。

微量要素は僅かな施用ですが大事な養分です。欠乏症状が現れないように定期的に施肥していきましょう。