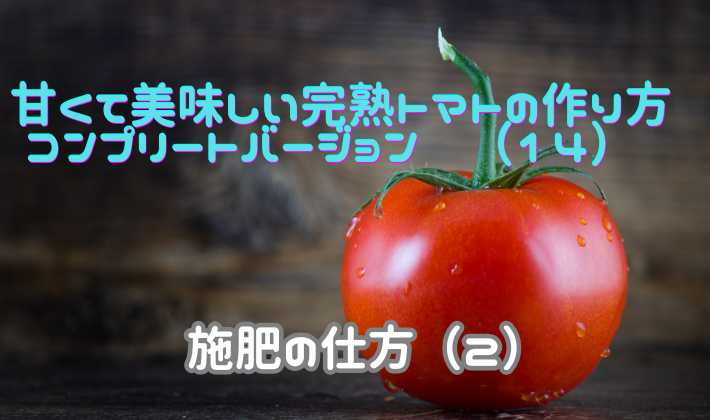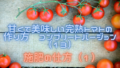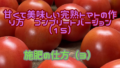イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方
イマジンファーム・アップルトマトのあるスギです。
今日は2月7日です。大玉トマト「ファイト」の収量も多くなって来て、収穫、出荷作業が忙しくなって来ました。
トマトの糖度も上昇してきました。長期促成栽培でトマトを作る場合、最も食味が良く、糖度が上昇するのは、3月〜4月です。
日が長くなり、光合成が活発になり、樹勢が活発になります。また、夜はまだまだ気温が低く、果実の生育もじわじわとゆっくり大きくなり、栄養素や果肉が濃縮して、コクと甘さと果汁いっぱいのトマトに仕上がって行きます。
5月に入ると日差しが強くなり、酸味が加わってきてます。水分要求量が多くなるので、水をたっぷり吸って、果実も味が淡白になってきます。
6月終わり位までは、甘くて美味しいトマトが作れます。しかし7月に入ると、ハウス内も気温が40度を超えてくるので、食味の良い、糖度の高いトマトが出来なくなります。
これからの時期、トマトが最も美味しくなる時期に入るので、私が作るトマトを食べてくださる方々が、喜んでくれる様なものを提供できるといいなと思っています。


今回は、実際使用している養液栽培用肥料の種類と特徴、オリジナル配合肥料の作り方について書いて行こうと思います。
養液栽培用肥料の種類と特徴
トマト栽培で使用する養液栽培用肥料の種類。
多量要素
硝酸カルシウム、硝酸カリウム、硫酸マグネシウム、第一リン酸カリウム
微量要素
キレート鉄、ホウ素、硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、モリブデン酸ソーダ
養液栽培用肥料の成分と特徴。
硝酸カルシウム Ca(NO₃)₂
成分
– 主成分: 硝酸カルシウム
– カルシウム(Ca²⁺)
– 硝酸態窒素(NO₃⁻)
– 形状: 白色の結晶性粉末や粒状。水に非常によく溶ける。
特徴
– 硝酸カルシウムは、植物にとって重要な栄養素であるカルシウムと窒素(硝酸態窒素)を同時に供給する肥料として広く利用されています。
– 特に、土壌中でカルシウム欠乏を補い、果物や野菜の品質向上(例:果実の腐敗防止)に寄与します。
硝酸カリウム KNO3
成分
– 主成分: 硝酸カリウム
– カリウム(K⁺)
– 硝酸(NO₃⁻)
– 形状: 無色または白色の結晶状固体。水に溶けやすい。
特徴
肥料としての利用
– 硝酸カリウムは、カリウムと窒素を同時に供給するため、農業用肥料として広く利用されています。
– 特に果樹や野菜、花卉(かき)栽培で重要で、作物の品質向上(果実の糖度向上、病害抵抗力の強化)に役立ちます。
安全性
– 硝酸カリウム自体は比較的安定していますが、火気や高熱の近くで扱うときは注意が必要です。可燃性物質と接触すると、燃焼を助長する可能性があります。
硫酸マグネシウム MgSO₄
成分
– 主成分: 硫酸マグネシウム
– マグネシウム(Mg²⁺)
– 硫酸(SO₄²⁻)
特徴
1. 肥料としての利用
– 硫酸マグネシウムは、マグネシウム不足を補う役割を果たします。
– マグネシウムは光合成に必要なクロロフィルの構成要素であり、植物の成長と発育に欠かせません。
– 硫酸イオンは硫黄の供給源としても機能します。
リン酸第一カリウム KH2PO4
成分
– 主成分: 第一リン酸カリウム
– カリウム(K₂O )
– リン酸(P₂O₅ )
– 形状: 無色または白色の結晶状固体で、水に溶けやすい。
特徴
– リン(P)は、根の発育や花芽形成、果実の品質向上に寄与します。
– カリウム(K)は、植物の耐病性や乾燥ストレスへの耐性を向上させるとともに、光合成や代謝を促進します。
キレート鉄 Fe
成分
– 主成分: 鉄
– 必須微量要素であり、植物の葉緑体合成や酵素反応に不可欠です。
– キレート剤で保護された形で存在し、植物が吸収可能な形状を維持します。
– キレート剤: 鉄イオンを包み込む役割を果たし、土壌環境での安定性を向上させます。主なキレート剤には以下のものがあります。
特徴
植物の鉄不足を補う
– キレート鉄は、植物にとって吸収可能な「可溶性鉄(Fe²⁺またはFe³⁺)を供給します。
– 鉄は光合成や呼吸作用で重要な役割を果たし、不足すると**葉が黄化**(クロロシス)するなどの症状が現れます。
土壌中での安定性
– キレート剤が鉄を保護し、不溶性の鉄化合物(酸化鉄など)への変化を防ぎます。
– 特にアルカリ性や石灰質の土壌では、通常の鉄肥料は吸収されにくいですが、キレート鉄は吸収可能な状態を維持します。
ホウ酸 H₃BO₃
成分
– 主成分:ホウ酸
– ホウ素(B)
– 水素(H)と酸素(O)
– 形状: 白色の結晶性粉末または無色の結晶。
– 溶解性: 水やエタノールに溶けやすい。水溶液では弱酸性を示します。
-特徴
植物栄養素としての役割
– ホウ素は、植物の細胞壁形成や花粉の発育、糖の輸送に不可欠な微量元素です。
– ホウ素欠乏が発生すると、作物の成長が悪化し、果実の品質や収穫量が低下することがあります(例: 茎や果実の奇形、花の未発達)。
硫酸マンガン MnSO₄
成分
– 主成分: 硫酸マンガン
– マンガン(Mn)
– 硫酸(SO₄²⁻)
-形状
– 一般的には薄いピンク色または白色の結晶状または粉末状。
特徴
植物の栄養素としての役割
– マンガンは、光合成の酵素反応や窒素代謝、抗酸化機構に重要な役割を果たします。
– マンガン欠乏症は、クロロシス(葉の黄化)や植物の成長不良を引き起こします。
– 硫酸マンガンは水溶性で植物に吸収されやすいため、効率的にマンガンを供給します。
硫酸亜鉛 ZnSO₄
成分
-主成分:
– 亜鉛(Zn)
– 硫酸(SO₄²⁻)
– 形状
– 無水物や水和物として存在。
– 水和物は、白色または無色の結晶性粉末
特徴
植物栄養素としての役割
– 亜鉛(Zn)は、酵素反応、タンパク質合成、ホルモン調節に重要な役割を果たします。
– 亜鉛欠乏症は、葉の小型化、成長遅延、クロロシス(葉の黄化)などを引き起こします。
硫酸銅 CuSO₄
成分
– 主成分: 硫酸銅
– 銅(Cu)
– 硫酸(SO₄²⁻)
– 形状
– 無水物または水和物として存在。
– 五水和物: 鮮やかな青色の結晶(一般的な形態)。
– 無水物: 白色または灰白色の粉末。
特徴
1. 植物の栄養素としての役割
– 銅は植物の酵素反応や光合成、リグニン形成に必要。
– 銅欠乏症は、葉の色抜けや茎の脆弱化、成長遅延を引き起こすことがあります。
– 硫酸銅は銅を供給する速効性の肥料として利用されます。
2. 殺菌・殺虫効果
– 硫酸銅は強い殺菌効果を持ち、農薬(殺菌剤)として利用されます。
– 特にボルドー液(硫酸銅と石灰の混合物)は、病害防除に効果的。
モリブデン酸ソーダ Na2MoO4・2H2O
成分
– 主成分: モリブデン酸ソーダ
– モリブデン(Mo)
– ナトリウム(Na)
– 形状
– 白色または無色の結晶性粉末。
– 無水物または水和物として存在(一般的には二水和物 )。
-特徴
1. 植物栄養素としての役割
– モリブデンは植物の窒素固定や硝酸還元に不可欠です。
– 特にマメ科植物では、根粒菌による窒素固定に重要。
– モリブデン欠乏は、硝酸の蓄積や葉の黄化、成長障害を引き起こすことがあります。

各要素の特徴をしっかり把握して、生育ステージに合わせた適正な施肥を目指しましょう。
オリジナル配合肥料(液肥)の作り方
用水の確保
用水の成分に合わせて肥料を配合します。
養液栽培で最も重要なことは良質な水を確保することです。
良質な水の条件は
1、pHが適正。
2、塩類濃度が低い。
3、有害物質を含まない。
4、病原菌を含まない。
5、粘土分を含まない。
などの条件を満たすものです。
用いられる水は
1、河川水
2、地下水
3、水道水
4、雨水
などが用いられます。
水質は意外と頻繁に変化するので、水質検査を定期的にして最新のデータをチェックする必要があります。
私の農場では、浅井戸と深井戸の2つの井戸から水を汲み上げています。
深井戸 EC0,6mS/cm
浅井戸 EC0,2mS/cm
海に近い場所で栽培しているので、深井戸の方はEC0,6mS/cmあり少し高いので、浅井戸と混ぜて使用しています。
ホウ素が若干高いので、培養液にホウ素は加えていません。
栽培する地域の水質によって、肥料の配合の仕方も変わってきます。水質に合わせた肥料の配合をしていきます。
液肥の作り方
私が実際に行なっている液肥の作り方を紹介します。
液肥作成用に、200ℓのタンクを2つ用意します。

液肥は1液と2液、2種類作り、潅水時に水と一緒に1液と2液を混ぜて施肥します。
リン酸および硫酸は、カルシウムと混ぜると沈澱を起こすので、別々のタンクで作ります。
1液は、硝酸カルシウム、硝酸アンモニウム、キレート鉄を溶かします。
2液は、硝酸カリ、硫酸マグネシウム、第一リン酸カリ、微量要素を溶かします。
培養液処方(窒素を100とした場合の比率)
| 化学式 | 比率 |
| NO3-N | 88 |
| NH4-N | 12 |
| K | 111 |
| P | 15 |
| Ca | 62 |
| Mg | 11 |
| S | 11 |
培養液作成法
| 肥料 | 標準 100倍原液 100ℓ | 2倍 200倍原液 200ℓ |
| 硝酸カルシウム | 6556g | 26224g |
| 硝酸カリウム | 4292g | 17168g |
| 硝酸アンモニウム | 1234g | 4936g |
| リン酸第一カリ | 1228g | 4912g |
| 硫酸マグネシウム | 2028g | 8112g |
| 鉄 | 4000g | 4000g |
| ホウ素 | 24g | 96g |
| 硫酸マンガン | 49g | 160g |
| 硫酸亜鉛 | 4、4g | 17、6g |
| 硫酸銅 | 1、6g | 6、4g |
| モリブデン | 0、4g | 1、6g |
基本、培養液は100倍原液を作りますが、私は200倍原液(200倍に希釈して使用する濃厚原液)を作成しています。
アンモニア態窒素の使用上の注意点
私は、窒素源としてのアンモニア態窒素は、基本使用していません。
アンモニア態窒素を加えると生育が促進されるが、アンモニアを過剰吸収し、障害を起こす場合があります。またカルシウムの吸収阻害を起こし、果実の尻ぐされを起こしやすいです。
もし使用する場合には、定植初期には施肥しないで、株が大きくなり生育が安定してからアンモニア態窒素を施肥した方が良いです。
アンモニア態窒素は、樹勢が弱って早く回復したい場合に、ピンポイントで使用します。
微量要素の使用上の注意点
養液土耕栽培の場合、土を使用するので、土の中に微量要素が含まれているし、緩衝力があるので、微量要素は加えなくても栽培は可能です。
しかし何かしら欠乏症状が現れてきたら、液肥に混入するか、葉面散布します。

次回は生育ステージによる施肥の仕方について書いていきたいと思います。