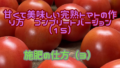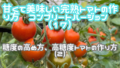イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方
イマジンファーム・アップルトマトのあるスギです。
今日は3月15日です。気温も少し高くなり、徐々に春らしい気候になり出しました。
トマトもだいぶ糖度が上昇して来て、甘く、コクがあり、ジューシーな食味になって来ました。
大玉トマト「桃太郎ファイト」 糖度8,85%


中玉トマト「フルティカ」 糖度9,15%


4月が一番糖度が高くなり、食味が良くなるので引き続き丁寧な水管理をして甘くて美味しいトマトを作っていこうと思います。

今回は糖度の高め方、高糖度トマトの作り方を書いていこうと思います。
はじめに
トマトの糖度とは、トマトに含まれる糖分の割合を示す指標であり、一般的に「Brix(ブリックス)」という単位で測定されます。例えば、糖度8のトマトは、果汁の8%が糖分であることを意味します。一般的なトマトの糖度は4〜6程度ですが、高糖度トマトと呼ばれる品種では8〜12、時には15以上のものも存在します。糖度が高くなると、甘みが増すだけでなく、酸味とのバランスも変わり、より濃厚で風味豊かな味わいになります。
では、なぜトマトの糖度が重要視されるのでしょうか?まず、味の向上が挙げられます。糖度の高いトマトは甘みが強く、フルーツのような味わいが特徴です。特に生食用のトマトでは、甘みと酸味のバランスが重要であり、糖度が高いほど美味しいと評価されることが多いです。また、加熱調理をする際にも、糖度の高いトマトは旨味が凝縮され、ソースやスープの味を引き立てます。
次に、市場価値の向上です。糖度の高いトマトは高級トマトとして販売されることが多く、一般的なトマトよりも高値で取引されます。例えば、高糖度フルーツトマトの価格は通常のトマトの2倍以上になることも珍しくありません。ブランド化されたトマトや特定の産地で育てられたトマトは、消費者の注目を集め、高級スーパーや直売所で人気を博しています。
さらに、栄養価の向上も糖度の高いトマトの特徴です。糖度が高いトマトは、糖分だけでなく、リコピンやビタミンC、カリウムなどの栄養素も豊富に含まれている傾向があります。リコピンは抗酸化作用が強く、生活習慣病の予防や美肌効果が期待される成分として知られています。また、ビタミンCは免疫力の向上に役立ち、カリウムは血圧の調整を助ける働きがあります。そのため、糖度の高いトマトを食べることは、健康面でもメリットが大きいのです。
今回は、トマトの糖度を高めるための具体的な方法を解説していきます。トマトの糖度を上げるには、品種の選び方、栽培環境の調整、水分管理、施肥、成熟度の管理など、さまざまな要素が影響します。それらのポイントを詳しく紹介しながら、初心者からプロの農家まで実践できる方法をお伝えします。

糖度の高いトマトを育てたい方にとって、役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。
トマトの糖度を決める要因
水分ストレスと糖度の関係
水分管理はトマトの糖度に大きな影響を与えます。特に、収穫期に適度な水分ストレスを与えることで、果実内の水分量が減少し、糖が濃縮されて甘みが増します。
具体的には、過剰な水やりを避け、やや乾燥気味に管理することで、糖度を高めることができます。ただし、極端に水を減らしすぎると成長が阻害されるため、適度なバランスが必要です。
光合成と糖の生成
トマトの糖度は、主に葉で行われる光合成によって作られる糖分の量に左右されます。光合成が活発に行われると、葉で生成された糖が果実に送られ、甘みが増します。そのため、太陽光をしっかり確保することが重要です。
特に、日照時間が長く、光量が十分に確保できる環境では光合成が活発になり、高糖度のトマトが育ちやすくなります。ハウス栽培の場合は、遮光しすぎないよう注意し、適度な換気を行うことで光合成効率を最大限に高めることがポイントです。
肥料のバランス
トマトの糖度を高めるためには、窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)のバランスを適切に調整することが重要です。
– 窒素(N):葉や茎の成長を促しますが、過剰になると葉ばかりが茂り、果実の糖度が低下するため注意が必要です。
– リン(P):根の発達を助け、果実の品質向上に貢献します。
– カリウム(K):糖の生成と果実への移動を促進し、糖度を上げるために不可欠です。収穫期にカリウムを多めに施すと、より甘いトマトが育ちます。
– カルシウム(Ca):細胞を丈夫にし、病気に強い果実を作ります。カルシウムが不足すると品質が低下しやすくなります。
-マグネシウム(Mg):光合成を助けるため、適量を与えると糖度向上につながる。
適切な施肥バランスを保ち、特にカリウムを重視した施肥設計を行うことで、糖度の高いトマトを育てることができます。
品種の選択
トマトの品種によって、糖度の上限が異なります。高糖度を狙う場合は、もともと糖度が高くなりやすい品種を選ぶことが効果的です。一般的な大玉トマトの糖度は4〜6程度ですが、高糖度トマトと呼ばれる品種では8以上になるものもあります。
私が実際に栽培している以下のような品種が高糖度トマトとして人気があります。
– 「アイコ」(ミニトマトで糖度が高く、果肉がしっかりしている)
– 「フルティカ」(甘みが強く、食味のバランスが良い中玉トマト)
– 「桃太郎ファイト」(糖度が高く、ジューシーな大玉トマト)
また、同じ品種でも栽培環境によって糖度は変わるため、適切な管理と組み合わせることで、より甘いトマトを育てることが可能になります。
成熟度と収穫タイミング
収穫のタイミングも糖度に影響します。
早摘み vs 完熟収穫
-早摘みしたトマトは糖度が低くなりがち。
-完熟収穫のほうが甘みが増すが、輸送や保存に注意が必要。
最適な収穫時期
-樹上で完熟したものを収穫すると糖度が最も高い。
-ヘタが黄色くなる直前が最も糖度が高くなるポイント。
着果処理の影響
着果促進のためにホルモン処理を施しますが、トマトトーン処理した場合、無処理に比べ糖度が上昇し、酸度が減少するという研究結果が出ています。
種子形成が糖度を減少させ、酸度を増加させるものと考えられます。
まとめ
トマトの糖度を高めるには、
1、水分管理でストレスを与える
2、光合成を活発にする
3、適切な肥料バランスを保つ
4、糖度の高い品種を選ぶ
5、収穫のタイミング
6、トマトトーン処理

という6つのポイントが鍵になります。これらを意識しながら、トマト栽培に取り組むことで、美味しく甘いトマトを育てることができるでしょう。
実践編①:高糖度トマトを作る為の環境管理の方法
トマトの糖度を高めるためには、栽培環境を最適に整えることが重要です。特に、「水管理」「日照時間」「温度管理」「栽培方法」の4つの要素が大きく関わります。ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
水管理のテクニック(水を少なめにしてストレスを与える方法)
トマトは水の管理によって糖度を大きく左右されます。特に「水を少なめに管理する」ことで、果実の水分が減り、糖が濃縮されやすくなります。
水を控えると糖度が上がる理由
-水分を制限するとトマトの細胞内の糖濃度が高まり、甘みが強くなる。
-植物がストレスを感じると、生存のために糖を蓄積する。
水分ストレスを与える方法
– 徐々に水を減らす:急激に水を減らすと生育不良を招くため、徐々に乾燥気味にするのがポイント。
– 収穫前の水管理:収穫の2週間前から水やりを制限し、果実の水分を減らすことで糖度を向上させる。
– 根を広げさせる:水を絞ることで根が深く広がり、栄養吸収が向上し、結果的に糖度が増す。
ただし、極端に水を減らしすぎると裂果や品質低下につながるため、土壌の状態を確認しながら調整することが重要
節水管理の重要性
私が実際にトマトを栽培していて感じるのは、トマトの糖度を高める要因はいろいろあるけど、最も重要な要因は水分ストレスだということです。
トマトの樹勢を落とさないようにしながら、どれだけ水を絞って水分ストレスを与えられるかがポイントになります。
節水管理しているトマトの根は、水を求めて培養土の中を四方八方、根を伸ばして水を得ようとします。自然と根張りが良くなり、根が活発に動く事で地上部の生育も促進されます。
水分ストレスを受けて、ストレスを耐え抜いたトマトは生命力が強くなり、急激な環境の変化や病害虫にも強くなります。
過酷な環境を潜り抜け、生命力が強いトマトから取れる果実は、糖度、酸度、各種栄養素がぎっしり詰まった果実になります。それがコクとジューシーさに繋がり、食味の抜群に良い、甘くて美味しいトマトになります。
日照時間の確保(ハウス栽培での調整、遮光対策)
トマトの糖度を高めるには、十分な光合成が不可欠です。日照時間が長く、光量が確保されるほど光合成が活発になり、糖の生成量が増えます。 同時に酸の生成量も増えます。
ハウスの環境管理
– 透明度の高いビニールを使用する:ハウスのフィルムが劣化すると光透過率が低下するため、適宜交換する。
– 遮光の調整:夏場の強すぎる直射日光は葉焼けを引き起こすため、可動式の遮光ネットを活用して調整する。
– 反射資材の利用:冬の日照不足を補うために、ハウスの地面に白い反射シートを敷くことで、葉の裏側にも光を当て、光合成を効率化する。
温度管理(昼夜の温度差を活かす)
トマトの糖度を上げるには、昼間の光合成で生成された糖を果実に蓄積させることが重要です。そのためには、昼夜の温度差を利用するのが効果的です。 昼夜の温度差が大きいと、糖の蓄積が進み、甘くなりなす。
温度管理のポイント
– 最適な温度範囲
– 昼間:25~30℃
– 夜間:12~18℃
→ 昼夜の温度差を10℃以上つけることで、夜間の呼吸量が減り、糖が消費されにくくなります。
ハウス栽培での温度調整
– 昼間は適切な換気を行い、高温になりすぎないよう管理する。
– 夏場の高温(35℃以上)は逆に糖度を下げるため、遮光や換気が必要。
– 冬場は地温を保つためにマルチシートを使用するのも有効。 夜間はハウスのビニールを二重にするなどして保温する。
– 1日8時間以上の日照が理想。
温度管理を適切に行うことで、光合成を活発にしつつ、糖の消費を抑え、高糖度のトマトを作ることができる。
私が行なっているトマトの長期促成栽培では、4月頃が最も気候的(日照、温度)にトマトの生育に適しており、糖度が高く、食味の良いトマトが出来上がります。
栽培方法の選択
トマトのハウス栽培には、土耕栽培、水耕栽培、ロックウール栽培など色々ありますが、私は養液土耕栽培を採用しています。養液土耕栽培の具体的な内容を以下に示します。
養液土耕栽培とは
養液土耕栽培(ようえきどこうさいばい)は、土壌を使いながらも液体肥料(養液)を供給する栽培方法です。通常の土耕栽培と水耕栽培の中間的な位置付けであり、作物の栄養管理を養液によって最適化します。
一般的に、ポット栽培や高設ベッド栽培などの形態で行われ、特にトマトやイチゴ、キュウリなどの果菜類の栽培に適しています。培地には黒ボク土、赤土、ピートモス、ヤシガラ、パーライトなどが使われ、排水性や通気性を考慮して設計されます。
養液土耕栽培の利点
土の恩恵を受けつつ、管理を最適化できる
– 土壌微生物の働きを活かせるため、病害抵抗力が高まる可能性がある。
– 水耕栽培と異なり、土のクッション機能(水分・養分の保持)があるため、急激な環境変化に強い。
養液管理による高収量・高品質
– 養分の供給をコントロールしやすいため、生育を安定させやすい。
– トマトの糖度向上など、目的に応じた施肥管理が可能。
– 生育ステージに合わせた施肥管理ができる。
– 限られた範囲に根を張らせることで、水分と養分の吸収を適度に抑え、果実に糖を蓄積させる。
– 培地にコンテナや丈夫な袋を使用しても栽培可能。根の成長をコントロールでき、高糖度トマト栽培が出来る。
水と肥料の節約
– 必要な量だけ養液を供給できるため、肥料の無駄を削減。
– 点滴灌水システムを利用すれば、水と養分を効率的に管理可能。
作業の省力化と自動化が可能
– 自動灌水装置やセンサーを導入すれば、管理の手間を軽減できる。
– 土耕に比べて雑草管理が楽で、除草作業が大幅に削減。
養液土耕栽培の欠点
初期設備費用が高い
– 自動灌水装置や養液管理システムを導入する場合、コストがかかる。
– 土壌分析や養液設計を適切に行う必要があり、専門知識が求められる。
養液管理を誤ると生育不良を招く
– 養液のバランスが崩れると、肥料焼けや欠乏症が発生しやすい。
– EC(電気伝導度)やpHのモニタリングが必要。
連作障害のリスク
– 土を使うため、病原菌や害虫が蓄積しやすい。
– 定期的な土壌改良(太陽熱消毒・客土・緑肥利用など)が必要。
停電や設備トラブルのリスク
– 養液供給が止まると、植物に影響が出る。
– バックアップシステムの整備が求められる
養液土耕栽培は、土の利点を活かしながら水耕栽培のような精密管理ができるという強みを持ちます。特にトマト栽培では、糖度管理や収量の向上に役立つため、商業的にも有利な技術です。
まとめ
トマトの糖度を高めるには、栽培環境を整えることが不可欠です。
1. 水やりを制限し、適度なストレスを与えることで糖度を上げる
2. 日照時間を確保し、光合成を最大限に活用する
3. 昼夜の温度差を利用し、夜間の糖消費を抑える
4. 養液土耕栽培など、管理しやすい、糖度を高めやすい栽培方法を選択する

4つのポイントを押さえてトマトの糖度を高めていきましょう!特に水管理は重要な作業になるので丁寧で繊細な管理を心がけましょう。
実践編②:高糖度トマトを作る為の肥料の施し方
トマトの糖度を上げるためには、適切な肥料のバランスを保つことが重要です。特に、窒素・リン・カリウムの適正な管理に加え、ミネラルや有機資材の活用が効果的です。本章では、トマトの甘みを引き出す施肥のポイントを解説します。
肥料の種類と使い方(窒素過多を避ける、カリウム強化)
トマトの糖度を高めるには、窒素(N)を抑えつつ、カリウム(K)を強化することが基本です。
窒素過多を避ける
窒素は葉や茎の成長を促しますが、多すぎると次のような問題が発生します。
– 葉ばかり茂り、実の成長が遅れる
– 糖度が低く、水っぽいトマトになる
– 病害虫が発生しやすくなる(特にうどんこ病)
そのため、着果が始まる段階で窒素の施肥を控えることが重要です。
カリウムの強化
カリウムは光合成を促進し、糖の合成と蓄積をサポートするため、糖度向上には欠かせません。
– 果実肥大期にカリウムを増やすことで糖度を上げる
– 葉の老化を防ぎ、光合成能力を維持する
– 根の働きを強化し、栄養吸収を助ける
施肥方法
-硝酸カリウム、リン酸第一カリウムを液肥として潅水
– カリウム主体の液肥を葉面散布
– カリウム過多にも注意(カルシウムやマグネシウムとのバランスが崩れると吸収障害が起こる)
ミネラルの活用(カルシウムやマグネシウムの影響)
トマトの甘さを引き出すためには、微量ミネラルのバランスが重要です。特にカルシウムとマグネシウムは、糖度を高めるために欠かせません。
カルシウム(Ca)
カルシウムは細胞を強化し、実の締まりを良くするミネラルです。カルシウムが不足すると、以下の問題が発生します。
– 実が割れやすくなる(尻腐れ病)
– 果肉が柔らかくなり、品質が低下する
施肥方法
-硝酸カルシウムを液肥として潅水
– 石灰(苦土石灰、消石灰)を元肥として土壌に混ぜる
– カルシウム液肥を葉面散布(例:卵殻を発酵させた液肥)
マグネシウム(Mg)
マグネシウムは光合成に関与するクロロフィルの主成分で、糖の生成を促進します。不足すると葉が黄化し、光合成効率が低下してしまいます。
施肥方法
– 硫酸マグネシウムを液肥として潅水
– 硫酸マグネシウム(エプソムソルト)を葉面散布
ミネラルのバランスを適切に整えることで、糖度を向上させるだけでなく、トマトの品質全体を向上させることができます。
有機資材の利用(アミノ酸、発酵堆肥、微生物資材)
化学肥料だけでなく、有機資材を活用することで、より自然に糖度を高めることが可能です。
アミノ酸肥料
アミノ酸は、トマトの生長を促進しながら糖度を向上させる働きがあります。特にグルタミン酸はトマトのうま味成分にもなり、甘みとコクを強化する効果があります。
施肥方法:
– アミノ酸肥料(魚かす、アミノ酸液肥)を追肥として使用
– 海藻エキスを葉面散布する(ミネラル補給と同時に糖度向上)
発酵堆肥の利用
発酵堆肥には微生物が豊富に含まれており、土壌の有機物を分解し、トマトが養分を吸収しやすくなる効果があります。特に、完熟発酵堆肥を使用することで、土壌微生物の活性を高め、根の健康を維持できます。
施肥方法
– マルチがわりに土の表面に撒く。この時、堆肥の厚さが5センチ位になるように撒く。 撒いた堆肥の上にマルチシートをひいて乾燥対策をする。
微生物資材の活用
微生物は、トマトの根の働きを活発にし、養分の吸収を助けるとともに、ストレス耐性を向上させます。
– EM菌 (有用微生物群)
施肥方法:500〜1000倍に希釈して灌水又は葉面散布
-えひめAI (乳酸菌、酵母菌、納豆菌)
施肥方法:500〜1000倍に希釈して灌水又は葉面散布
-光合成細菌
施肥方法:500〜1000倍に希釈して灌水する。
まとめ
1. 窒素を抑え、カリウムを強化することで糖度を向上
2. カルシウムとマグネシウムを適切に補給し、光合成を促進
3. アミノ酸や発酵堆肥、微生物資材を活用し、自然に糖度を上げる

肥料を与えすぎには注意しましょう。病害虫に弱くなるし、食味も悪くなります。トマトの様子を毎日よく観察して最適な施肥管理をしていきましょう。