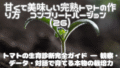イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方
はじめに
トマト栽培において、最も大切なのは「観察力」です。
高品質なトマトを安定して育てるためには、単に水をやり、肥料を与えるだけでは不十分です。植物は言葉を発しませんが、その姿かたち、葉の色、茎の太さ、花の様子など、すべてが“サイン”です。私たち栽培者は、そのサインを見逃さずに読み取る「眼」を育てる必要があります。
かつては、熟練農家の勘と経験がものを言う時代でした。朝露の具合を見て潅水の量を調整したり、葉の色だけで窒素過不足を判断したりと、五感をフルに使って作物と向き合っていたのです。しかし、気候変動や土壌の変化、品種の多様化、さらには市場のニーズの変化により、経験則だけでは対処しきれないケースが増えてきました。
今、農業は大きな転換点に立っています。温度、湿度、日射量、CO₂濃度、土壌養分…あらゆる環境要素がセンサーで可視化され、数値で管理できる「精密農業」「データ農業」の時代へと進化しています。こうした技術の進歩により、トマトの生育状態をより正確に把握し、問題が起きる前に予兆を察知し、最適なタイミングで対処できる可能性が広がっています。
しかし、ここで忘れてはいけないのは、「診断」は単に“異常を見つける”ためだけのものではないということです。むしろ、健全に育っているかどうか、草勢は理想の状態か、どの段階でストレスがかかっていたのか――“成長の軌跡”をつぶさに見極めることこそ、生育診断の真の目的です。
診断とは「育てることそのもの」と言い換えてもよいでしょう。トマトがどんな状態にあるのかを毎日見つめ、その変化に耳を傾け、的確に対応していく。その繰り返しこそが、結果的に美味しく、安定した収穫へとつながります。
本ブログでは、トマト栽培における「生育診断」の基本的な考え方から、具体的な観察ポイント、データ活用法、異常時の対処法までを体系的に紹介していきます。トマトと対話するように、日々の“観察”を積み重ねる――それが、プロの農業者としての第一歩なのです。
トマトの「理想の姿」を知る
生育診断の第一歩は、「理想の姿」を知ることです。
どこに向かって育てていくのか、そのゴールが見えていなければ、いくら目の前のトマトを観察しても、その状態が良いのか悪いのか判断できません。トマト栽培には、生育ステージごとに「理想的な草姿(そうし)」があります。それを基準として、日々の変化を見極めていくのです。
● ステージごとの理想モデル
【1】発芽・育苗期

双葉が開き、最初の本葉が出てくるこの時期、ポイントは「徒長していないか」です。茎がヒョロヒョロと伸びていたら、光量不足や過湿が疑われます。理想は、葉が地面と水平に広がり、茎は太くて短く、全体がガッチリとした姿です。
【2】定植直後(活着期)

根がしっかりと張り、葉が上を向いてくるのが理想です。葉がダラリと垂れている、萎れている、色が薄いといった症状がある場合、根の活着がうまくいっていない可能性があります。逆に、急激に草勢が強まりすぎると、後の着果に悪影響が出るため注意が必要です。
【3】栄養成長期(草勢充実)

草丈が順調に伸び、葉も大きく展開していくこの時期は、節間が適度に詰まり、茎がしっかりと太く、葉色が鮮やかな緑色であることが理想です。節間が長すぎれば過繁茂の兆候、逆に短すぎれば肥料や水分不足の可能性があります。
【4】生殖成長期(開花〜着果)

花房が整い、花が大きく咲いている状態が理想です。花が小さい・落ちる・花数が少ないといった兆候は、ストレスや栄養バランスの崩れを表しています。また、主枝と側枝のバランスも重要で、茎葉ばかり育って花が疎かになるような“暴れ”に注意が必要です。
【5】果実肥大期・成熟期

果実が均一に肥大し、色づきが揃っていることがポイントです。実の肥大が不揃い、割れがある、先端が黒ずむなどの症状があれば、水分の急変やカルシウム不足、生理障害の兆しと見てよいでしょう。
● 理想を知ることで「違和感」が見える
理想の姿を知るということは、日々の栽培の中で「違和感」に気づけるようになるということです。例えば、ある日の葉色が“ほんの少しだけ薄い”と感じたとします。素人目には問題ないように見えても、理想と比較して違和感があれば、それは初期のストレス反応かもしれません。
この“違和感を見抜く眼”こそが、生育診断の要です。そしてそれは、頭の中に「理想の姿」という型があることで初めて養われていきます。
生育診断の基本手法
理想の草姿をイメージできたら、次は「今の状態」がその理想にどれほど近づいているかを判断する必要があります。
そのために用いるのが「生育診断」の基本手法です。診断は大きく分けて4つのステップ、「目視」「触診」「計測」「記録」によって構成されます。
目視 ― トマトの“表情”を読む
目視は最も基本かつ重要な観察手法です。
トマトは言葉を話せませんが、葉の色や形、茎の太さや節間の長さ、花の咲き方、実の大きさなどに、日々の環境や管理に対する反応を“正直に”表しています。
観察ポイント:
- 葉の色とツヤ:薄すぎれば肥料不足、濃すぎれば過繁茂の兆候。マットな質感は低温や病害のサイン。
- 茎の太さ:直径8〜10mm程度が目安。細すぎれば草勢不足、太すぎれば暴れの兆候。
- 節間の長さ:間延びしていれば光不足や肥料過多、詰まりすぎていれば成長停滞の可能性。
- 花房の状態:花の大きさ、数、色などに注目。正常なら規則的に咲き、落花が少ない。
- 果実の様子:大きさ、着果数、形、色づきのバランス。裂果や尻腐れがないかも確認。
触診 ― 作物の“声なき声”を感じ取る
見た目だけではわからないこともあります。そこで重要なのが「触れること」。
実際に手で茎を握り、葉を触り、花や実に指先で触れてみると、その質感やハリから健康状態を把握できることがあります。
触診ポイント:
- 茎のしなやかさ:硬すぎるとストレスがかかっている証拠。柔らかすぎるのも要注意。
- 葉の張り:ピンと張っているのが理想。しおれていたり、ベタつく感じがあると水分や病気に問題あり。
- 花の感触:触ってポロッと落ちるようなら着果不良の兆候。
触れることで作物との距離が縮まり、変化に対する「直感力」が磨かれます。農業は“肌感覚”も大事なスキルなのです。
計測 ― 感覚を「数値化」する
目視と触診に加えて、数値で管理することが精密な診断には欠かせません。
「なんとなく弱い」ではなく、「茎径が6mmしかない」「SPAD値が35以下」といった具体的な数値で示すことで、他の株との比較や時系列での変化の把握が可能になります。
主な計測項目:
- 茎径:定規またはノギスで測定
- 節間の長さ:株の状態により変化する
- 草丈:生育スピードの把握に有効
- 葉緑素濃度(SPAD値):専用の計測器で葉色を数値化(目視では分からない変化の察知)
- 温度・湿度・日射量:センサー設置でハウス内環境の見える化
- 土壌EC・pH:肥料の効き具合やpH適正のチェック
データ化された数値は、記録し比較することで、そのトマトが「例年より良いのか悪いのか」、「水や肥料を変えた結果がどう出たか」を明確にする材料になります。
記録 ― “感覚”を“蓄積された知恵”に変える
いくら観察しても、それが記録に残らなければ、ただの「その場限りの気づき」で終わってしまいます。
生育診断を真の武器にするには、日々の記録が不可欠です。
おすすめの記録方法:
- チェックシート式:週1回、生育項目を○△×で記録するだけでもOK
- 写真記録:スマホで葉や花、果実を定点撮影(1株だけでも)
- 手帳・アプリ・Excel:作業メモと一緒に記録するのがコツ
たとえ一見正常でも、「例年より開花が1日遅い」「花数が去年より少ない」といった“微差”の積み重ねが、収量や品質に大きな差を生みます。
生育診断は“育てる”ことそのもの
診断とは、病気や問題を見つけることではなく、成長を見守るための対話手段です。
目で見て、手で触れて、数字で確かめて、記録に残す――。これらすべてが合わさって、私たちは「トマトを知る眼」を養っていくことができます。
症状別・生育診断ガイド
どれだけ理想の草姿や観察手法を知っていても、実際の現場では「なんだかおかしいぞ?」という瞬間が必ず訪れます。
そこで役立つのが、症状から原因を逆算する診断力です。
この章では、トマトに現れやすい代表的な“症状”ごとに、その背景にある問題や考えられる要因を具体的に解説していきます。
感覚的な「なんとなく変」から一歩踏み込んで、「○○が××だから△△の兆候だ」と言えるようになるのが、プロの生育診断です。
葉の色と形 ― 作物の“気分”が表れる場所
【症状1】葉が黄色くなる
- 主な原因:窒素不足、老化、根の障害、低温
- 見分け方:下葉から黄化する場合は自然な老化や軽度の窒素不足。新葉まで黄変している場合は深刻な根のトラブルが疑われます。
【症状2】葉が濃すぎる、ツヤがない
- 主な原因:窒素過剰、日射不足、過湿
- 注意点:色が濃いから健康とは限りません。光合成が不足していたり、養分が偏っている可能性あり。
【症状3】葉が紫色になる
- 主な原因:リン酸不足、低温ストレス
- 補足:特に初期生育期に多く見られ、苗の温度管理がポイント。夜温が10℃を下回ると発症しやすい。
【症状4】葉がカールする・縮れる
- 主な原因:高温乾燥、ウイルス感染、カルシウム欠乏
- 見極め:急な天候変化であれば一時的だが、株全体に広がる場合はウイルスや生理障害の疑い。
茎と節間 ― 草勢と根の状態が見える
【症状5】茎が細い/徒長している
- 主な原因:光量不足、水分不足、根の活着不良
- 対応:遮光しすぎていないか、土壌が過湿で根腐れしていないかをチェック。
【症状6】茎が太すぎる・硬すぎる
- 主な原因:窒素過剰、草勢過多、灌水過多
- 診断のコツ:「暴れ」の前兆。花が飛びやすくなり、収穫期が遅れがちになる。
【症状7】節間が詰まりすぎる/間延びする
- 詰まりすぎ:生育停滞、寒さ
- 間延び:肥料過多、温度過多、暗さ
- 対処法:ハウス内の温度・日照・潅水を総点検
● 花と果実 ― 生殖成長のバロメーター
【症状8】花が小さい・数が少ない
- 主な原因:ストレス(水・温度)、草勢アンバランス
- 改善策:窒素の見直し、潅水の均等化、着果促進剤の適正使用
【症状9】花が落ちる(落花)
- 主な原因:乾燥・多湿の急変、高温、受粉不良
- 注意点:マルハナバチの活動不足や、人工受粉のタイミングミスも要因になる
【症状10】実が大きくならない/肥大が不揃い
- 主な原因:ホルモン不均衡、肥料切れ、カルシウム不足
- 補足:着果数が多すぎると肥大が分散する。摘果のバランスが鍵
【症状11】実が割れる(裂果)
- 主な原因:水分変動、根圧急変、雨よけ管理ミス
- 改善策:潅水を急に増やさない。果実肥大期は潅水を一定に保つ
【症状12】尻腐れ果(カルシウム欠乏)
- 主な原因:カルシウム不足、吸収不良(乾燥・高EC)
- 対策:石灰資材の投入、葉面散布、EC管理、潅水管理の見直し
● トマトのSOSに気づく診断表(簡易チェック)
| 症状 | 考えられる主な原因 | 優先チェック項目 |
| 葉が黄変 | 窒素不足/根の不良 | 土壌水分・肥料成分 |
| 花が落ちる | 温度変動/受粉不良 | ハウス内温度・マルハナバチ活動 |
| 実が割れる | 潅水急変/根圧急上昇 | 潅水間隔・天候変化 |
| 茎が暴れる | 窒素過多/潅水過多 | 施肥設計・水管理 |
このように症状を整理し、視覚・触覚・数値で多角的に原因を探ることで、精度の高い診断が可能になります。
日々の“違和感”を蓄積せよ
生育診断は一発勝負ではありません。
「昨日より少し茎が硬い」「2日前より葉がやや黄ばんでいる」――こうした微細な変化の積み重ねこそ、トマトの訴えを聞き取る手がかりになります。
次回に続きます。